日常生活継続支援加算は、要介護度が高い方や認知症の方など、重度のご利用者を積極的に受け入れる特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)を評価するために設けられた制度です。
適切に算定することで施設の収益向上につながるだけでなく、質の高いケアを提供できる体制が整っていることの証明にもなります。
この記事では、日常生活継続支援加算の対象サービス、単位数、算定要件、必要な手続きなどについて解説します。
目次
日常生活継続支援加算とは

日常生活継続支援加算は、重度の要介護者や認知症のご利用者の受け入れを促進するために創設された加算です。
自宅での生活が困難になった高齢者に対し、特養が積極的に入所を受け入れ、適切なケアを提供することを評価します。
日常生活継続支援加算を算定するには、介護福祉士を一定数以上配置することが求められます。また、満たすべき条件もあるため、算定要件をしっかりと確認することが大切です。
2021年度の介護報酬改定では、見守り機器やインカムなどのテクノロジーを活用する場合に、介護福祉士の配置要件が緩和されました。これにより、業務の効率化を図りながら、ケアの質を維持・向上させることが可能になっています。
日常生活継続支援加算は特養独自の加算であり、公益社団法人全国老人福祉施設協議会の調査によると、算定率は約79.5%と非常に高い水準です※。
※参照:公益社団法人全国老人福祉施設協議会 令和4年4月加算算定状況等調査の結果の概要について
多くの特養がこの加算を算定しており、重度者の受け入れと質の高いケア提供に取り組んでいることが分かります。
日常生活継続支援加算の対象サービス
日常生活継続支援加算の対象となるのは、
・介護老人福祉施設(特養)
・地域密着型介護老人福祉施設(地域密着特養)
の2つです。
なお、併設または空床利用型のショートステイは、日常生活継続支援加算の対象外となりますので注意が必要です。
介護老人福祉施設(特養)
介護老人福祉施設は、定員30人以上の広域型特養を指します。複数の市区町村にまたがる広域からご利用者を受け入れることができる施設です。
従来型(多床室)とユニット型(個室)のどちらも対象となりますが、加算の種類が異なります。
・従来型:日常生活継続支援加算(Ⅰ)
・ユニット型:日常生活継続支援加算(Ⅱ)
を算定します。
施設の入所定員による上限はなく、30人規模の施設でも100人を超える大規模施設でも算定可能です。
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着特養)
地域密着型介護老人福祉施設は、定員29人以下の小規模特養です。
原則として、施設がある市区町村に居住している要介護3以上の方が入所対象となります。
地域に密着した小規模なケアを提供する施設として位置づけられていますが、日常生活継続支援加算の算定要件は通常の特養と同じです。
規模が小さくても、重度のご利用者を受け入れ、介護福祉士を適切に配置していれば算定できます。
従来型は日常生活継続支援加算(Ⅰ)、ユニット型は日常生活継続支援加算(Ⅱ)を算定する点も、介護老人福祉施設と同様です。
テクノロジー活用による要件緩和

2021年度の介護報酬改定で、見守り機器やインカムなど複数のテクノロジー機器を活用する場合に、介護福祉士の配置要件が緩和される仕組みが導入されました。
業務効率化を図りながらケアの質を維持・向上させることが目的です。
2021年改定での変更点
人員配置基準が6:1から7:1へ緩和されましたが、単位数は変更ありません。
人員配置基準の緩和内容
通常は入所者6人に対し介護福祉士1人以上ですが、テクノロジー活用時は入所者7人に対し1人以上に緩和されます。
緩和を受けるには、複数種類の介護機器を使用し、多職種協働でアセスメントと評価を行い、安全体制を確保する必要があります。
対象となるテクノロジー機器
複数種類の介護機器を使用することが条件です。1種類だけでは要件を満たしません。
対象機器は、業務効率化・質向上・職員負担軽減に資するものです。
具体的には、見守り機器、インカム、記録ソフト、移乗支援機器などが該当します。
導入すべきICT機器・テクノロジー
実際に特養で活用されている主な機器を紹介します。
導入にあたっては、介護ロボット導入支援事業などの補助金も活用できます。
見守り機器
ベッド上のご利用者の動きや呼吸をセンサーで感知する機器です。
起き上がりや離床を検知し、転倒・転落リスクを早期に発見できます。
夜間の定期巡視の頻度を減らせるため、職員の負担軽減とご利用者の睡眠確保の両立が可能です。
異常を検知した際は、インカムと連携して迅速に対応できます。
インカム
職員間でリアルタイムにコミュニケーションできる通信機器です。
見守り機器と連携し、異常検知時に即座に情報共有できます。
離れた場所にいる職員を呼びに行く時間が不要になり、緊急時の対応が早まります。
日常的な情報共有も効率化され、チームケアの質が向上します。
記録ソフト等のICT
介護記録を電子化し、タブレットやスマートフォンで入力できるシステムです。
ご利用者のそばで記録を完結でき、事務室に戻って手書き記録を清書する時間が不要になります。
記録の共有がリアルタイムで行え、申し送りの時間短縮や情報伝達ミスの防止につながります。
LIFEへのデータ提出も効率化されます。
移乗支援機器
リフトやスライディングシートなど、ご利用者の移乗を支援する機器です。
職員の腰痛予防に効果があり、安全に介護できる環境を整えます。
ご利用者にとっても、無理な力がかからず安全に移乗できるメリットがあります。
抱え上げによる不安や痛みを軽減し、ケアの質向上につながります。
安全体制の確保方法
テクノロジー活用による要件緩和を受けるには、委員会の設置と職員研修の実施が必須です。
委員会の設置
介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置します。
介護職員、看護職員、介護支援専門員など多職種で構成し、定期的に開催します。
委員会では以下の事項を検討・確認します。
・ ご利用者の安全とケアの質の確保
・ 職員の負担軽減と勤務状況への配慮
・ 介護機器の定期的な点検
・ 効果検証と改善策の検討
多職種協働でアセスメントと評価を行い、必要に応じて職員配置や機器の使い方を見直します。
職員研修の実施
介護機器を安全に使用するための研修を定期的に実施します。
新規職員への研修も含め、全職員が適切に機器を扱えるようにします。
研修内容には、機器の操作方法、異常時の対応、ご利用者への配慮などを含めます。
研修の実施記録を保管し、実地指導の際に提示できるようにしておきます。
算定に必要な手続きと書類
日常生活継続支援加算を算定するには、都道府県(または市区町村)への届出が必要です。
届出から算定開始までの流れと、算定開始後の管理業務について解説します。
届出が必要な書類
基本の届出書とテクノロジー活用時の追加書類があります。
日常生活継続支援加算に関する届出書
加算を算定する際の基本となる届出書です。
施設の基本情報、算定要件の充足状況(新規入所者の状態、介護福祉士の配置数など)を記載します。
届出書の様式は、都道府県や市区町村のホームページからダウンロードできます。
記載方法が分からない場合は、担当窓口に確認しながら作成しましょう。
テクノロジー導入時の追加書類
7:1配置(テクノロジー活用による要件緩和)を選択する場合は、「テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書」も提出します。
この届出書には、導入している介護機器の種類、委員会の設置状況、職員研修の実施状況などを記載します。
基本の届出書とあわせて、両方を提出する必要があります。
提出期限と手続きの流れ
届出書を提出する際には余裕を持った準備が重要です。
届出のタイミング
原則として、算定を開始する月の前月15日までに届出を提出します。
例えば、4月から算定を開始する場合は、3月15日までに提出が必要です。
ただし、施設サービスの場合は、算定月の初日までに受理される必要があります。
提出後の審査期間を考慮し、早めに提出しましょう。
新規開設の施設は、開設後4か月目から届出が可能です。
前3か月の実績を基に算定要件を満たしているかを確認します。
審査から承認までの期間
提出した書類は、都道府県または市区町村で審査が行われます。記載内容に不備があれば差し戻されるため、提出前に十分確認しましょう。
通常は数日から2週間程度で受理されますが、繁忙期や書類に不備がある場合はそれ以上かかることもあります。
算定開始月の初日に間に合うよう、余裕を持って提出することをお勧めします。
算定開始後の管理業務

日常生活継続支援加算の算定開始後も、継続的な管理が必要です。
毎月の要件確認
算定要件を満たし続けているか、毎月確認する義務があります。
新規入所者の要介護度、認知症自立度、医療処置の状況を記録し、重症度要件を満たしているか確認します。
介護福祉士の配置数も毎月確認します。
退職や異動により配置基準を下回っていないか、常勤換算で計算しましょう。
確認結果は記録に残し、実地指導の際に提示できるようにしておきます。
記録の保管義務
算定根拠となる記録を整備し、保管する義務があります。
保管すべき記録は以下の通りです。
・ 新規入所者の要介護度、認知症自立度、医療処置に関する記録
・ 介護福祉士の資格証の写しと勤務実績
・ テクノロジー活用時は、委員会の議事録と職員研修の記録
これらの記録は、実地指導で確認されることがあります。
整理して保管し、いつでも提示できるようにしておきましょう。
要件を満たさなくなった場合の対応
算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出の取り下げを行う必要があります。
要件を満たさなくなった月の翌月から加算を算定できません。
例えば、4月に要件を満たさなくなったことが判明した場合、5月分からは加算を算定できなくなります。
誤って算定を継続した場合、過誤請求となり返還が必要です。
日常生活継続支援加算は単位数が高いため、返還額も大きくなる可能性があります。
要件を再度満たせるようになれば、改めて届出を行い、再算定が可能です。
新規入所者の状態や介護福祉士の配置状況を改善し、要件を満たせる体制を整えましょう。
日常生活継続支援加算の注意点
日常生活継続支援加算の算定時に注意すべきポイントを確認しておきましょう。
サービス提供体制強化加算との同時算定不可
日常生活継続支援加算を算定している場合、サービス提供体制強化加算は算定できません※。
※参考:厚生労働省「301 介護老人福祉施設サービス費(要件一覧)」
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士や実務者研修修了者などの有資格者の配置割合を評価する加算です。
どちらの加算を選択すべきかは、施設の状況によって異なります。
日常生活継続支援加算は(Ⅰ)が36単位、(Ⅱ)が46単位と単位数が高い一方、重症度要件があります。
特養のサービス提供体制強化加算は単位数は日常生活継続支援加算と比較すると、(Ⅰ)22単位、(Ⅱ)18単位、(Ⅲ)6単位と低めではありますが、要件が比較的緩やかです。
重度のご利用者を積極的に受け入れている施設は、日常生活継続支援加算の方が収益面でメリットがあるでしょう。
ただし、新規入所者の状態によって要件を満たせない月がある場合は、サービス提供体制強化加算との切り替えも検討できます。
月ごとに加算を切り替えることは可能ですが、その都度届出の変更が必要です。
頻繁な切り替えは事務負担が大きいため、安定的に算定できる加算を選択することをお勧めします。
日常生活継続支援加算 FAQ
実務上よくある疑問について、厚生労働省の介護保険最新情報を参考に回答します。
Q: 入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生活継続支援加算の算定要件における新規入所者に含めてよいか。
A: 入院中も引き続き、退院後の円滑な再入所のためにベッドの確保等を行い、居住費等を徴収されていた者については、新規入所者には含めない。
(参考:厚生労働省「介護サービス関係Q&A」平成27年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1 問126)
Q: 日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点のものと加算の算定月のもののどちらを用いるのか。
A: 入所時点の要介護度や日常生活自立度を用いる。
(参考:厚生労働省「介護サービス関係Q&A」平成27年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1 問129)
Q: 「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。
A: 「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。
(参考:厚生労働省「介護サービス関係Q&A」平成24年3月16日版 vol.267 問196)
まとめ
日常生活継続支援加算について分かりやすく解説しました。
日常生活継続支援加算は、重度のご利用者を積極的に受け入れる特養を評価する重要な加算です。
算定要件は、施設基準、重症度要件、介護福祉士の配置基準の3つの柱から構成されています。
2021年改定で導入されたテクノロジー活用による要件緩和を活用すれば、介護福祉士の配置基準が6:1から7:1に緩和することも可能です。
日常生活継続支援加算は、施設の安定的な運営と質の高いケア提供につながる加算です。
見守り機器やインカムなどの複数の機器を導入することは、ご利用者と介護職員にとってより良い介護環境を実現することにつながります。
この記事の執筆者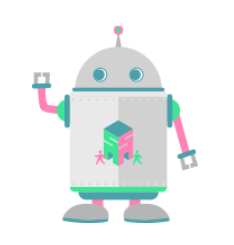 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。





















