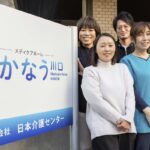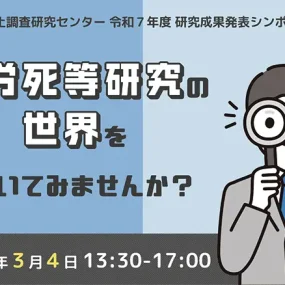介護現場における介護リーダーは、介護主任やユニットリーダーなど、施設によって名称は様々ですが、共通して「人間関係の悩みを抱えやすい」といった傾向がみられます。
介護リーダーは現場の業務をこなす一方で、シフトの作成や調整、人員配置、スタッフの教育や育成、管理者とのパイプ役など、業務のバリエーションは多岐に渡り、さらに上司と部下の板挟みになったり、利用者や家族への対応などストレスも多く、人間関係のストレスを抱えやすい立場です。
この記事では、介護リーダーが直面しやすい人間関係の悩みについて具体的に解説し、それらの原因と対処法を紹介します。
介護リーダーとして現場で悩みを抱えている方が、一歩前進するためのヒントとなれば幸いです。
目次
介護現場の人間関係は悪くなりやすいって本当?
介護の仕事をしていると、「職場の人間関係に悩んでいる」「介護現場の雰囲気が良くない」という声をよく耳にします。
実際に、厚生労働省関連機関による最新の調査『令和5年度介護労働実態調査 P.27』によると、介護の仕事を辞めた理由の第1位は「職場の人間関係の問題」で、全体の34.3%を占めています。
これは前年度よりも6.8ポイント増加しており、人間関係の悪化が介護業界における深刻な課題となっていることを示しています。
しかしながら、すべての介護施設で人間関係が悪いわけではありません。
職場の雰囲気が悪くなる原因には、スタッフ同士のコミュニケーション不足、過度な業務負担、慢性的な人手不足など原因があります。
介護現場では、職員間だけでなく利用者やその家族とも日常的に多くのコミュニケーションをとる必要があります。そのため、一人ひとりのストレスが蓄積すると、些細なことでトラブルが生じ、結果的に職場全体の雰囲気が悪化してしまうことがあります。
こうした状況が慢性化すると、スタッフの離職が増え、さらに人手不足が深刻になるという悪循環を招きます。
介護リーダーは、その中で人間関係の問題に対して積極的に対応し、職場環境を整えていく役割を担っているため、悩みや負担を感じやすい立場にあります。
そのため、介護リーダーが人間関係に関する悩みに対処し、良好な職場環境を維持する方法を知っておくことは非常に重要です。
介護リーダーはなぜ人間関係に悩みやすいのか

介護リーダーが人間関係に悩みやすいのは、介護業界特有の構造的な問題が背景にあります。特に以下のような要因が重なり、ストレスが蓄積しやすくなっています。
・業務量の多さ
日常の介護業務に加え、シフト調整やスタッフ指導、人員配置など多岐にわたる役割を担い、残業や休日出勤が増える傾向にあります。
・人手不足と補充の困難
欠員が出てもすぐに人材を確保できず、リーダー自身が現場を支え続けなければならないことが多く、心身の余裕を失いやすくなります。
・注意や指導のしづらさ
「辞められたら困る」と思うあまり、スタッフへの指導をためらい、曖昧な対応が誤解や不満を招くことも。
・上司と部下の板挟み
双方の意見を調整する立場にあり、精神的なプレッシャーを感じやすくなります。
・多様な人材への対応
異業種からの転職者や年上の新人スタッフへの接し方・指導に悩み、コミュニケーション不足が発生しやすい状況です。
このような複合的な要因によって、介護リーダーは職場の人間関係に悩みを抱えやすい立場にあるといえるでしょう。
介護現場の環境改善には、介護リーダーの負担を軽減する施策も重要です。
職場全体の問題と捉えてコミュニケーションを改善する対策を行う一方、職場のICT化も有効な施策となるでしょう。
特にシフト作成に数時間~数十時間をかけている施設の場合、シフト作成ソフトの導入は効果的ですので、ぜひ検討をおすすめします。ICT事例も参考にしてみてください。
介護リーダーが悩みを抱えやすい理由
介護リーダーが抱えやすい悩みについて、詳しく見ていきましょう。
人手不足でリーダーもスタッフも余裕がない

介護現場では慢性的な人手不足が続いており、介護リーダーもスタッフも精神的・身体的に余裕を失いがちです。
リーダーは日常業務に加え、スタッフ教育やシフト調整、緊急対応など業務が多岐にわたり、業務時間内にすべてを終えるのは難しく、残業や休日出勤が常態化している介護現場も多いでしょう。
特に介護リーダーはスタッフが急に欠勤したり、退職したりすると、率先してシフトに入り、穴を埋めることも少なくありません。休日にも職場からの連絡が入り、気持ちが休まらない状況も多くあります。
また、スタッフ側も業務の多忙さから余裕がなくなり、小さな誤解や不満が大きなトラブルに発展しやすくなります。
リーダーが業務に追われると、本来の役割であるスタッフへのサポートが不足し、職員間の不満やストレスが高まるという悪循環が生まれてしまいます。
コミュニケーションが不足している
介護リーダーは、職員同士だけでなく、他部署、多職種、利用者家族など幅広い立場の人と関わるため、高いコミュニケーション能力が求められます。
しかし、介護スタッフの年齢や経験は多様で、リーダーが年下であったり、後から入社した場合など、立場や年齢差によってコミュニケーションが難しくなることがあります。
特に、年上のスタッフに注意や指導を行う際には、相手に不快感を与えないよう気を遣うリーダーも多いでしょう。そのため、積極的なコミュニケーションを避けてしまう可能性もあります。
その結果、職員間の意思疎通が不足し、誤解や不満を生み出す要因となってしまいます。
また、リーダーが多忙な業務に追われていると、必要最低限の連絡だけになりがちで、お互いの意図が伝わらず職場の雰囲気が悪化することもあります。
このようにコミュニケーション不足は職場に大きな問題をもたらす原因の一つとなります。
上司と部下の板挟みになりやすい
介護リーダーは、施設長や管理者など上司からの指示をスタッフに伝える役割と、スタッフの意見や要望を上司に伝える役割の両方を担っています。
そのため、上司と部下との間で板挟みになることが多く、精神的な負担を抱えやすい立場にあります。
上司からは業務効率化や人員配置、スタッフへの指導などの具体的な指示が出されますが、現場スタッフからは人手不足や業務過多、職場環境への不満が寄せられます。
こうした対立する意見や要望を調整し、双方に納得してもらうことは非常に難しく、リーダーが大きなストレスを感じる原因になります。
板挟みの状況が続くと、リーダー自身も判断力やモチベーションが低下し、職場全体の雰囲気にも影響を及ぼしてしまいます。
スタッフの一人ひとり、価値観や経験が異なるから
介護業界では、異業種からの転職者や40代・50代で入社する新人スタッフも多く、職場には多様な価値観や経験を持つスタッフが共に働いています。
そのため、介護リーダーがスタッフに指導や注意をする際、意図しない誤解や反発を招くことがあります。
特に年上のスタッフに対しては、「偉そうだ」と感じさせてしまわないかと、慎重になりすぎてコミュニケーションが不足してしまうケースも多く見られます。
また、スタッフそれぞれの勤務希望や働き方の違いに対応するため、シフト作成にも気を遣い、自分の休暇は後回しになりがちです。
個人の要望と現場の事情を調整する難しさから、シフトを作ることにストレスを感じるリーダーも少なくありません。
人間関係に悩む介護リーダーの対処法とは

介護リーダーとして人間関係の悩みが深刻化すると、「リーダーを辞めたい」と感じることもあるかもしれません。リーダー職は責任が重く、精神的な負担も大きいため、そのような気持ちを抱くのは自然なことです。
しかし、突発的に辞めることは問題の根本的な解決にならず、転職先でも同じ悩みを繰り返す可能性があります。まずは一度立ち止まり、自分が抱える悩みの具体的な原因を整理し、冷静に対処法を考えてみましょう。
介護リーダーの人間関係の悩みは、職場環境やコミュニケーション不足、スタッフの多様性などさまざまな要因が絡み合っています。これらを改善するためには、単に個人の努力だけでなく、組織としての取り組みや周囲のサポートも重要になります。
介護リーダーが実践できる具体的な対処法を以下に紹介します。
悩みの原因を整理し、適切な対応策を一つずつ実践することで、ストレスが軽減され、職場の人間関係も改善へと向かうでしょう。
人間関係の何に悩んでいるのか明確にしてみる
人間関係に悩んだときは、まず「自分が人間関係の何に悩んでいるのか」を具体的に明確にすることが大切です。
誰との関係なのか、どのような場面でストレスを感じているのか、業務内容に関することなのか、それとも相手の言動に原因があるのかなど、悩みの中身を細かく分類してみましょう。
例えば、「あの人と合わない」と漠然と感じている場合でも、実は指示の出し方が一方的だったり、勤務態度に不満があるといった具体的な原因が隠れていることがあります。
そうした問題を言語化して可視化することで、冷静に対策を考えやすくなります。
悩みを紙に書き出す、箇条書きで整理する、といった作業も効果的です。
頭の中だけで考えていると、感情に流されて視野が狭くなってしまうことがありますが、書き出して整理することで問題の核心が見えやすくなります。
問題が明確になれば、対処法も自然と導きやすくなります。漠然とした不安を抱えるよりも、「どこをどう改善すればよいのか」が分かることは、精神的な負担を軽減する第一歩になります。
コミュニケーションをこまめにとる
人間関係の悩みを改善するうえで、最も基本的かつ効果的なのが「こまめなコミュニケーション」です。
介護の現場では、業務の忙しさから必要最小限の会話だけで済ませてしまうことが多く、相手の気持ちや意図が伝わらずに誤解が生まれやすくなります。
特に、指導や注意をする場面では、リーダーの意図が正しく伝わっていないと「きつい言い方だった」「感情的だ」と受け取られてしまうこともあり、関係が悪化する原因になりかねません。
そのため、日頃から相手の考え方や感じ方に関心を持ち、話す機会を意識的に増やすことが大切です。
また、コミュニケーションは一方通行ではなく、双方向であることが重要です。相手の話をしっかり聞き、共感や理解を示すことで、信頼関係が築かれていきます。
リーダーとしての立場にとらわれすぎず、時にはフラットな目線で会話をすることで、より良い関係性が生まれやすくなります。
「苦手だな」と感じる相手とも、会話を重ねるうちに意外な共通点が見つかり、関係が改善することもあります。まずは小さな声かけや日常会話から始め、職場内の雰囲気づくりを意識してみましょう。
無理をしない、適度に距離を取る
どれだけ努力しても、人間関係がうまくいかない相手がいることも事実です。そんなときは、無理に関係を改善しようとせず、「仕事上の関係」と割り切って、適度な距離を取ることも一つの選択肢です。
介護の現場では、チームワークが求められる反面、すべての職員と深く関わらなければならないわけではありません。業務に必要な範囲でのやりとりを丁寧に行い、プライベートな感情を持ち込みすぎないことが、精神的な余裕を保つためには有効です。
たとえば、シフトを調整して関わる時間を減らす、休憩時間を別々にするなど、物理的な距離をとる工夫も有効です。業務上の連携は冷静に、丁寧に対応しながら、必要以上に関わらないことで、お互いに過剰なストレスを感じずに済むようになります。
適度な距離感を保つことで、心に余裕が生まれ、目の前の仕事に集中しやすくなります。
「うまく付き合わなければ」と意識し過ぎず、必要な距離を取ることも、介護リーダーとしての大切なセルフケアの一つです。
自分自身のストレスマネジメントをする
介護リーダーは多忙な業務と人間関係の板挟みの中で、知らず知らずのうちに大きなストレスを抱えてしまいがちです。
そのまま放置すると、心身の不調やバーンアウトに繋がる可能性もあるため、自分自身のストレスを適切に管理する「ストレスマネジメント」が重要です。
まずは、自分に合ったリフレッシュ方法を見つけましょう。読書、散歩、音楽、趣味など、仕事以外の時間を有意義に過ごすことで、心に余裕が生まれます。また、運動はストレス解消に非常に効果的で、軽いストレッチやウォーキングでも気分転換になります。
悩みを一人で抱え込まず、信頼できる人に話すことも大切です。家族や友人だけでなく、職場の同僚や他部署のスタッフなど、同じ環境にいる人との共有は気持ちを整理する助けになります。
可能であれば、介護リーダー同士の情報交換の場やオンラインコミュニティに参加するのもよいでしょう。
また、職場全体でストレス対策に取り組むことも必要です。定期的な面談や相談窓口の設置、心身の健康チェックなど、管理職や組織による支援体制の構築が、リーダーの安心感につながります。
自分自身のストレスチェックをする場合、ストレスチェックシートを活用するとよいでしょう。以下の記事で、オンラインで手軽に利用できるストレスチェックシートを紹介していますので、参考にしてみてください。
上司に相談する
人間関係の悩みを一人で抱え込まず、上司に相談することも大切な対処法の一つです。施設長や管理者といった上司に話すことで、客観的なアドバイスを受けられたり、自分では気づかなかった視点に気づけることがあります。
「上司には話しづらい」と感じる人も多いかもしれませんが、基本的に上司は職場全体の運営を円滑に進めることが役割であり、現場で起きている問題を早めに知りたいと思っています。深刻な事態になる前に相談してもらうことは、むしろ歓迎される行動です。
相談する際には、感情的にならず、事実と気持ちを整理して伝えるよう心がけましょう。「どのような場面で」「誰との関係に」「どんな困りごとがあるか」など、具体的に伝えることで、上司も適切な対応を取りやすくなります。
また、悩みを共有することで、上司がリーダーの置かれた状況を理解し、日頃の業務や人間関係に配慮してくれるようになる可能性もあります。関係性が築かれていれば、いざという時の精神的な支えにもなるでしょう。
深刻な状況になる前に、早目のタイミングで相談することが大切です。
まとめ
介護リーダーとして働くなかで、人間関係に悩むことは珍しくありません。職員間の年齢や経験の差、業務負担の大きさ、上司と部下の板挟みなど、複数の要因が絡み合い、悩みを深めてしまうこともあります。
しかし、悩みを放置せず、まずは「何に悩んでいるのか」を明確にし、冷静に向き合うことが大切です。それにより、対処の糸口が見えてくるでしょう。
また、こまめなコミュニケーションや適度な距離の取り方、ストレスマネジメントなど、自分に合った対処法を見つけることも大切です。
職場全体で悩みを共有し、信頼できる上司や仲間に相談することも、負担を軽減する大きな助けになります。
リーダーという立場だからこそ、自分一人で何でも背負い込むのではなく、周囲のサポートを活用する柔軟さも大切です。
人間関係の悩みは、介護現場の空気やチーム力に直結します。小さな取り組みの積み重ねが、働きやすい職場づくりにつながり、自分自身の成長ややりがいにもつながっていくはずです。
自分らしいリーダーシップを見つけ、よりよい人間関係を築いていくための一歩を、ぜひ踏み出してみてください。
| この記事の執筆者 | ペコ 保有資格:介護福祉士 介護支援専門員 これまで通所リハビリに2年、小規模多機能型居宅介護に17年勤務。その中でも小規模多機能では介護職4年、介護福祉士兼介護支援専門員を3年、管理者兼介護支援専門員を9年務め、現在は代表も兼任しています。 介護の話題を中心にライタ―活動を行っており、他には介護用の研修資料の作成なども行っています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。