介護施設では利用者の安全確保が最優先事項です。そのため、制度面でも安全対策を促進する仕組みとして「安全管理体制未実施減算」が設けられています。
この減算制度は、適切な安全対策を講じていない施設に対して介護報酬が減額されるもので、現場の安全管理体制の整備を推進する重要な役割を果たしています。
本記事では、安全管理体制未実施減算についてわかりやすく解説し、算定要件や対象サービス、関連する加算制度である安全対策体制加算についても紹介します。
目次
安全管理体制未実施減算とは?

安全管理体制未実施減算とは、介護施設が運営基準で定められた「事故の発生または再発を防止するための措置」を適切に講じていない場合に適用される減算制度です。高齢者や要介護者を対象とする介護施設では、転倒・誤嚥・紛失などの事故リスクが高く、それらを防止するための体制整備が求められています。
この制度は令和3年度(2021年度)の介護報酬改定で新設され、同年4月から施行されました。ただし、施設側の準備期間として2021年9月30日まで6か月間の経過措置期間が設けられました。この期間終了後、安全管理体制が基準を満たさない施設が減算の対象となっています。
安全管理体制未実施減算の導入背景
この減算制度の導入背景には、介護施設における事故防止対策の強化と、利用者の安全確保を組織的に推進することが目的としてあります。単に事故が起きた後の対応だけでなく、事前の予防策や再発防止のための仕組み作りを促進する狙いがあります。
組織的に安全対策の体制作りを整えることが求められ、単なる事故後の対応だけでなく、「未然に防ぐ」仕組み作りを重視している点が特徴といえるでしょう。
安全管理体制未実施減算の対象サービス
安全管理体制未実施減算の対象となるのは以下の施設系サービスです。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・特定施設
実際の該当状況について、厚生労働省の調査によると、安全管理体制未実施減算に該当する事業所は特養で1.5%、老健で2.9%となっています。この数字からも、多くの施設では既に必要な安全管理体制が整備されていることがわかります。
参照:(2)介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業(結果概要)(案) P.3
しかし、依然として一部の施設では体制整備が不十分であり、特に「安全対策担当者の設置」がネックとなっているケースが多いようです。介護人材不足が続く中、専門的な知識を持つ担当者の配置が課題となっているといえそうです。
安全管理体制未実施減算の算定要件

安全管理体制未実施減算の算定要件は、以下の4つの基準をすべて満たしていない場合に適用されます。つまり、これらの要件のうち一つでも満たしていなければ減算の対象となります。
1. 事故発生防止のための指針の整備
事業所では、介護事故を未然に防ぐためのガイドラインや、万が一、介護事故が発生した場合の対応手順などを文書化した指針を整備する必要があります。この指針には、事故発生時の対応フローや報告方法などを具体的に記載し、職員がいつでも確認できるようにしておくことが重要です。
2. 事故発生時の報告と分析を通じた改善策の周知体制の整備
介護事業所において、事故やヒヤリハットが発生した場合の報告体制を整え、それらの事例を分析して再発防止策を検討する仕組みを構築する必要があります。また、単に報告するだけではなく原因を分析し、そこから得られた改善策を全職員に周知徹底することが求められます。また、自治体への報告が必要な事故の場合は、速やかに所定の様式で報告することも求められています。
3. 事故発生防止のための委員会及び職員研修の定期的な実施
施設内に事故発生防止委員会を設置し、定期的に会議を開催して事故防止策や再発防止策を検討する必要があります。また、事故発生防止委員会を中心として、全職員を対象とした事故防止のための研修を定期的に実施し、その内容や参加者を記録として残すことも求められます。
4. 上記措置を適切に実施するための担当者設置
事業所内に安全対策担当者を配置し、上記1〜3の措置を適切に実施・管理する体制を整える必要があります。安全対策担当者は、外部のリスクマネジメント研修を受講することが望ましいとされています。特に選定基準は定められてはいませんが、安全管理に関する知識を持った人材を配置することが重要といえるでしょう。
これらの要件は単独ではなく、一体的に整備することで効果を発揮します。いずれか一つでも満たしていない場合は減算対象となりますので、すべての要件を満たす体制づくりが必要です。
安全管理体制未実施減算の単位数
安全管理体制未実施減算が適用される場合、1日につき5単位が所定単位数から減算されます。施設種別を問わず、一律で5単位/日となっています。
一見少額に思えるかもしれませんが、この減算は1日単位で適用されるため、例えば50人定員の施設で全利用者が1ヶ月(30日)減算を受けると、5単位×50人×30日=7,500単位となります。1単位10円として計算すると75,000円/月の減収となり、年間では90万円の減収につながります。
安全管理体制未実施減算が適用された場合、日々の累積で大きな金額になる可能性があります。また何より、利用者の安全を守るための体制が整っていないと評価されることは、施設の信頼にも関わる問題だといえるでしょう。
安全対策体制加算との関係性
安全管理体制未実施減算と対をなす制度として「安全対策体制加算」があります。これは安全対策が適切に行われている施設を評価する加算で、入所時に1回限り20単位が算定できます。
安全対策体制加算については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
安全管理体制を整備するためのステップ
介護事業所で安全管理体制を適切に整備し、安全管理体制未実施減算の適用を避けるためにはどういった手順で進めていくと良いでしょうか。一例として、以下のようなステップで体制作りを進められるでしょう。
1. 現状分析とチェックリストの活用
まずは、自施設の安全管理体制の現状を分析します。茨城県筑西市が公開している「安全管理体制未実施減算及び安全対策体制加算チェックリスト」などを活用すると効率的です。
参照:「安全管理体制未実施減算」及び「安全対策体制加算」について|筑西市公式ホームページ
2. 安全対策担当者の選任と研修
施設内で安全管理に適した人材を選び、安全対策担当者として選任します。可能であれば、外部研修を受講させることで、より専門的な知識を身につけることができます。
3. 事故発生防止のための指針の整備
事故発生時の対応フローや報告方法、再発防止策の検討方法などを明記した指針を作成します。
4. 事故発生防止委員会の設置と定期開催
事故発生防止委員会を設置し、定期的に会議を開催する体制を整えます。委員会では、ヒヤリハットや事故報告の分析、再発防止策の検討などを行います。
5. 職員研修の実施と記録
全職員を対象とした事故防止のための研修を計画的に実施し、その内容や参加者を記録として残します。
6. 報告・分析・改善のサイクル確立
事故やヒヤリハットが発生した際の報告体制を整え、それらを分析して改善策を全職員に周知する仕組みを確立します。このPDCAサイクルを継続的に回すことが重要です。
まとめ
安全管理体制未実施減算は、介護施設における安全管理体制の整備を促進するために設けられた制度です。4つの基本的な要件(指針整備、報告・分析体制、委員会・研修実施、担当者設置)を満たさない場合、1日あたり5単位が減算されます。
逆に、より高度な安全管理体制を整備した施設は、安全対策体制加算として入所時1回20単位を算定できます。これらの制度は単なる報酬の問題ではなく、利用者の安全を確保するという介護の基本に関わる重要な事項です。
安全管理体制の整備は、単に減算を避けるためだけでなく、利用者に安心・安全なサービスを提供するという介護の本質に関わる取り組みです。本記事で紹介した内容を参考に、自施設の安全管理体制を見直し、より質の高いケアの実現につなげていただければ幸いです。
この記事の執筆者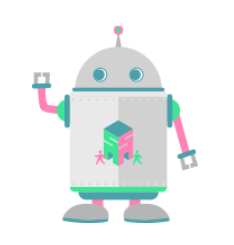 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。





















