経口維持加算とは介護保険施設において、中度から重度の要介護者や認知症高齢者に対して、より質の高い口腔ケアに取り組むための制度です。
摂食・嚥下機能の低下により経口摂取が困難になりつつある入所者に対して、食事の楽しみを維持するための支援を評価する加算制度です。
この記事では、経口維持加算の概要、算定要件、単位数、対象者や算定時の注意点など、わかりやすく解説します。
目次
経口維持加算とは
経口維持加算は、入所者が認知機能や摂食・嚥下機能の低下により経口での食事摂取が困難になった場合でも、食事による楽しみを得られるよう多職種が協力して支援することを評価する加算です。
経口維持加算は、単に収益を増やすだけでなく、入所者のQOL(生活の質)向上という重要な目的を持っています。
経口維持加算が創設された背景として、高齢者にとって「口から食べること」が生活の質(QOL)や楽しみの上で非常に重要である一方、加齢や疾患で嚥下機能が低下すると誤嚥性肺炎のリスクも高まるという課題があります。
また、経口での食事摂取は単に栄養を摂るだけでなく、食の楽しみや社会的交流の機会としても重要な意味も持ちます。
経口維持加算は、そうした食事の持つ多面的な価値を守るための取り組みを推進するものとなります。
経口維持加算の対象サービス
経口維持加算は全ての介護サービスで算定できるわけではなく、特定の施設サービスが対象となります。
【施設サービス】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
【地域密着型サービス】
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特養)
これらの施設サービスを対象としている加算です。経口維持加算は入所者に対する継続的な栄養・嚥下支援を評価するものなので、利用者が施設等に入所していることが前提となります
経口維持加算の算定要件
経口維持加算を算定するためには、前提条件を満たした上で、加算の種類に応じた要件を満たす必要があります。
経口維持加算を算定するための前提条件
経口維持加算を算定するには、まず以下の5つの前提条件をすべて満たす必要があります。
1.通所介護費算定方法に規定する基準に該当しないこと
2.入所者の摂食・嚥下機能が医師により適切に評価されていること
3.誤嚥が起こった場合の管理体制が整備されていること
4.食べやすく工夫した食事など、誤嚥防止のための配慮がなされていること
5.医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員、その他の職種による協働体制が整っていること
経口維持加算(Ⅰ)の算定要件
経口維持加算(Ⅰ)は400単位/月の加算であり、主に以下の要件を満たす必要があります。
1.上記の前提条件をすべて満たしていること
2.医師または歯科医師の指示のもと、多職種が共同して入所者の栄養管理のための食事観察・会議などを行い、対象者ごとに経口維持計画を作成していること
3.医師または歯科医師の指示に基づき、経口維持計画に従って管理栄養士や栄養士が適切な栄養管理を実施していること
経口維持加算(Ⅱ)の算定要件
経口維持加算(Ⅱ)は100単位/月の加算で、加算(Ⅰ)に追加して算定できるものです。
1.協力歯科医療機関が経口維持加算(Ⅰ)を算定していること
2.入所者の栄養管理のための食事観察・会議などに、医師、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士のいずれか1名以上が参加していること
経口維持加算の単位数
経口維持加算の単位数は以下の通りです。
| 加算の種類 | 単位数 | 備考 |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 | 基本となる加算 |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/月 | 加算(Ⅰ)に追加して算定可能 |
経口維持加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
経口維持加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の主な違いは以下の点です。(Ⅰ)は基本的な経口維持支援に対する評価であり、(Ⅱ)は専門職参加によるさらなる充実に対する評価といえます。
・経口維持加算(Ⅰ)は基本となる加算で、多職種による食事観察と会議の実施、経口維持計画の作成が要件
・経口維持加算(Ⅱ)は協力歯科医療機関を定め、専門職(医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士)が食事観察や会議に参加した場合の追加加算
経口維持加算を算定する際の注意点
経口維持加算を算定するにあたり、以下のような点に気を付ける必要があります。
① 毎月のミールラウンドと多職種会議の実施(必須)
・対象者の食事状況(嚥下状態や食べ方、むせ込みの有無など)を毎月1回以上、実際に観察します(ミールラウンド)。
・観察結果をもとに、多職種(医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護職員など)が参加する会議を毎月1回以上開催します。
・会議やミールラウンドの記録(実施日・参加者・評価結果)を必ず残すことが必要です。
・医師、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士のいずれか1名以上が参加している場合、経口維持加算(Ⅱ)が算定できます。
② 栄養アセスメントシートへの記録の徹底
・対象者ごとに栄養状態や嚥下機能を評価し、栄養アセスメントシートに記録します。
・経口維持計画の内容(食形態、栄養量、ケア内容など)を明確に記録・管理します。
・定期的に評価を見直し、記録の更新を怠らないよう注意します。
③ 同意の取得、計画内容の変更時は家族の再同意を得る
・経口維持計画は本人や家族の同意が必要です。また、食事形態や嚥下リハビリ内容など、経口維持計画に変更が生じる場合は、必ずご本人や家族に変更内容を説明し、再度同意を得る必要があります。
・同意を得た日時や説明した担当者名も記録しておくと安心です。
④栄養マネジメント強化加算を算定している施設が前提
・経口維持加算は栄養マネジメント加算を算定している施設で行うことが前提です。
経口移行加算と経口維持加算の違い
経口維持加算と混同されやすい「経口移行加算」についても、その違いを押さえておきましょう。
| 項目 | 経口維持加算 | 経口移行加算 |
| 対象者 | 経口摂取をしているが機能低下により困難になっている方 | 在経管栄養で食事を摂取している方 |
| 目的 | 経口摂取の維持・継続 | 経管栄養から経口摂取への移行 |
| 単位数 | 400単位/月(加算Ⅰ)、100単位/月(加算Ⅱ) | 28単位/日 |
なお、経口維持加算と経口移行加算は同時に算定することはできませんので注意が必要です。
まとめ
経口維持加算は、摂食・嚥下機能の低下した入所者の経口摂取を支援するための重要な加算制度です。入所者のQOL向上に寄与するだけでなく、施設の収益改善にも貢献します。
加算取得のためには、
1. 対象者の適切な選定と評価
2. 多職種連携による食事観察と会議の実施
3. 経口維持計画の作成と実施
4. 定期的な評価と見直し
これらのプロセスを確実に実施することが重要です。経口維持加算の算定には手間がかかる面もありますが、入所者の食事の楽しみを守り、QOLを向上させるという意義は大きいものだといえるでしょう。
ぜひ施設の体制を整え、積極的に取り組んでいただければと思います。
この記事の執筆者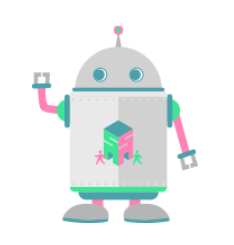 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。





















