口腔連携強化加算は、令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で新設された制度です。
訪問介護や訪問看護、ショートステイなどでご利用者の口腔状態を評価し、その情報を歯科医療機関やケアマネジャーに共有することで算定できます。算定は月1回、50単位となります。
誤嚥性肺炎や低栄養の予防、咀嚼・嚥下機能の維持など、日常生活の質を高める効果が期待されています。
一方で、評価方法や連携体制の整備、届出の手順など、現場には分かりづらい点も少なくありません。
ここでは、制度の目的や対象、算定要件から注意点まで、厚生労働省の資料をもとにわかりやすく解説します。
目次
口腔連携強化加算とは
口腔連携強化加算は、介護サービス提供時にご利用者の口腔状態を評価し、その情報を歯科医療機関やケアマネジャーに提供することで算定できる加算です。
令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で新設され、訪問介護や訪問看護、短期入所など幅広いサービスが対象となります。
制度の目的は、口腔ケアを通じて咀嚼・嚥下機能の維持や誤嚥性肺炎の予防を図ることにあります。
ここでは、新設の背景、目的と効果、そして現状の課題について整理したいと思います。
2024年度介護報酬改定で新設された背景
この加算が新設された背景には、高齢者の口腔機能低下が全身の健康に与える深刻な影響があります。
口腔機能の低下は摂食嚥下機能の低下を招き、栄養状態の悪化や誤嚥性肺炎のリスクを高めることが医学的に証明されています。
特に要介護高齢者においては、適切な口腔ケアが実施されないことで、これらのリスクがさらに高まる傾向にあります。
厚生労働省は、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的実施の重要性を強調しており、この三要素が相互に作用することで、より効果的な介護サービスの提供が可能になるとしています。
口腔連携強化加算は、この一体的実施を実現するための具体的な制度として位置づけられています。
加算の目的と期待される効果(ケア品質向上・誤嚥防止など)

この加算の目的は、定期的な口腔状態の評価と情報共有により、ご利用者の口腔機能維持・改善を図ることです。
口腔内の清潔を保つことで咀嚼や嚥下機能を守り、誤嚥性肺炎や低栄養のリスクを軽減できます。
また、介護職員が日常的に口腔の変化に気づく習慣を持つことで、異常の早期発見や医療介入につながり、ケア全体の品質向上にも寄与します。
口腔機能は食事や会話など日常生活の質に直結するため、加算を活用した取り組みはご利用者の生活満足度向上にもつながります。
これらは、リハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的実施の考え方と密接に関連しており、包括的なケアの提供につながります。
高齢者の口腔ケアが抱える現状課題(実診率の低さなど)
現在の介護現場では、口腔ケアに関する専門的な知識や技術の不足が大きな課題となっています。
調査によると、口腔連携強化加算の算定実績がある介護事業所は、調査対象1,605施設のうち37施設(2.3%)※にとどまっています。
この低い算定率の背景には、複数の要因が考えられます。
連携可能な歯科医療機関の確保が困難である事業所が多いこと。また、口腔の健康状態評価を実施できる職員の育成が追いついていない現状があります。
さらに、評価項目の理解や記録方法について、現場での戸惑いも見られます。
高齢者の口腔ケアは非常に重要です。これらの課題を解決し、より多くのご利用者が適切な口腔ケアを受けられる環境の整備が急務となっています。
参照:一般社団法人 日本老年歯科医学会 訪問系及び短期入所サービスにおける 口腔の連携強化に㛵する調査研究事業事業報告書 P.7
口腔連携強化加算の対象サービス

口腔連携強化加算は、訪問系サービスや短期入所系サービスなど、複数の介護サービスで算定できます。
いずれも、ご利用者の口腔状態を評価し、歯科医療機関やケアマネジャーへ情報提供することが条件となります。
口腔連携強化加算算定できる事業者は、以下となります。
・訪問介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
口腔連携強化加算の対象者
口腔連携強化加算の対象となるご利用者には、特定の条件や制限はありません。各対象サービスを利用するすべてのご利用者が算定対象となります。
ただし、算定にあたってはご利用者の同意が必要であり、口腔健康状態の評価と情報提供について十分な説明を行うことが重要です。
ご利用者やご家族への説明では、口腔健康の重要性と全身への影響について分かりやすく伝え、歯科医療機関との連携によるメリットを具体的に説明することが大切です。
評価結果は医療機関とケアマネジャーに情報提供されることも含めて、丁寧に同意を得る必要があります。
口腔連携強化加算の算定要件
口腔連携強化加算の算定には、3つの必須要件を満たす必要があります。
・看護師等がご利用者の口腔健康状態の評価を実施すること
・ご利用者の同意を得て歯科医療機関及びケアマネジャーに評価結果を情報提供すること
・歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医師又は歯科衛生士と相談できる体制を確保すること
口腔健康状態の評価は、事業所の従業者が実施することとされています。
具体的にどの職種が評価を行えるかについては、サービス種別や事業所の体制により異なりますが、看護師等の専門職が中心となって実施することが想定されています。
評価は月1回を上限として実施し、同一月内での重複算定はできません。
歯科医療機関との連携体制については、事前に文書による取り決めを行うことが求められます。
連携先となる歯科医療機関は、歯科訪問診療料の算定実績があることが必要で、地域の歯科医師会等を通じて適切な連携先を確保することが重要です。
情報提供は、厚生労働省が定める様式を用いて行い、評価実施後速やかに実施する必要があります。
情報提供先のケアマネジャーとの連携も重要で、口腔ケアを含めたケアプラン見直しの検討材料として活用されることが期待されています。
口腔連携強化加算の単位数
口腔連携強化加算の単位数は、『50単位』に設定されています。
算定頻度は月1回に限定されており、同一月内での重複算定はできません。
歯科医療機関との連携体制構築
口腔連携強化加算の算定において最も重要な要素の一つが、歯科医療機関との連携体制の構築でしょう。
連携歯科医療機関の選定から具体的な連携方法まで、段階的に体制を整備していく必要があります。
連携歯科医療機関の選定基準として、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定実績があることが求められます。
これは、在宅歯科医療の経験と実績を有する歯科医療機関との連携により、より実効性の高い支援体制を構築するためです。
文書による取り決めでは、相談・助言の具体的な方法、対応時間、緊急時の連絡体制などを明確に定める必要があります。
情報提供の方法や頻度、秘密保持に関する事項についても、詳細に取り決めることが重要です。
実際の連携では、事業所職員からの相談に対して、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が適切に対応する体制を確保します。
定期的な情報交換や研修会の開催なども、連携体制の強化に効果的です。
連携体制は一度整えれば終わりではなく、定期的に内容を見直し、実務に即した形に更新することが重要です。
様式、情報提供書について
厚生労働省では、口腔連携強化加算の円滑な実施を支援するため、標準的な様式を提供しています。
これらの様式を活用することで、事業所は効率的に情報提供や記録管理を行うことができます。
主な様式として、「口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書」があります。
この様式には、8項目の評価結果を記載する欄が設けられており、歯科医療機関やケアマネジャーとの情報共有に活用されます。
また、各自治体では届出書の様式も整備されており、加算の算定開始前に適切な届出を行う必要があります。
これらの書類は、介護報酬の請求時にも重要な根拠資料となります。
厚生労働省の公式サイトでは、最新の様式がダウンロード可能な形で提供されています。更新される場合もあるため、常に最新版を使用するとよいでしょう
口腔連携強化加算における、アセスメントの方法

口腔連携強化加算で実施する口腔の健康状態評価は、厚生労働省が定める8つの評価項目に基づいて行われます。
各項目は、介護職員でも実施可能な観察方法と明確な判定基準が設定されており、専門的な器具を使用せずに評価できます。
評価項目は以下の通りです。
| 評価項目 | 評価のポイント | 判定基準 |
| 開口 | 口の開き具合 | 指2本分(縦)入らない場合は「できない」 |
| 歯の汚れ | 歯の表面の清潔度 | 白や黄色の汚れがある場合は「あり」 |
| 舌の汚れ | 舌の表面の清潔度 | 白、黄色、茶、黒色の汚れがある場合は「あり」 |
| 歯肉の腫れ・出血 | 歯肉の健康状態 | 腫れや出血がある場合は「あり」 |
| 左右両方の奥歯でしっかり噛みしめられる | 咀嚼機能 | 噛みしめられない場合は「できない」 |
| むせ | 摂食嚥下機能 | むせがある場合は「あり」 |
| ぶくぶくうがい | 口腔機能 | 水をためておけない場合は「できない」 |
| 食物のため込み・残留 | 摂食嚥下機能 | ため込みや残留がある場合は「あり」 |
評価実施時には、ご利用者のプライバシーに配慮し、リラックスした環境で行うことが重要です。また、評価結果は客観的に記録し、継続的な変化の把握に活用します。
口腔連携強化加算の留意点
口腔連携強化加算を算定する際には、制度上の制限や現場で生じやすい課題に注意する必要があります。
要件を満たしていても、併算定禁止や記録の不備などで加算が認められないケースがあります。
ここでは、特に押さえておくべき留意点をまとめます。
併算定できない加算
・口腔・栄養スクリーニング加算
・居宅療養管理指導
また、他の介護事業所がすでに当該利用者について口腔連携強化加算を算定している場合、重複して算定することはできません。
現場における算定への課題
・時間確保の難しさ
月1回の評価実施と記録作成が業務負担になる場合があります。
・評価スキルの差
評価の精度が職員によって異なると、情報の信頼性に影響します。
・連携先の確保
地域によっては歯科医療機関との連携が難しい場合があります。
・同意取得のハードル
ご利用者やご家族に制度の意義を理解してもらう必要があります。
これらの課題に対応するためには、評価シートの活用や職員研修、歯科連携ネットワークの構築など、事業所全体での工夫が求められます。
口腔連携強化加算における多職種連携の重要性
口腔連携強化加算の効果的な活用には、多職種間の密接な連携が不可欠です。
各職種の専門性を活かした協働により、ご利用者により質の高い口腔ケアを提供することができます。
介護職員は、日常的なケアの中でご利用者の口腔状態の変化を観察し、適切な評価を実施。
看護職員は、医療的な視点から口腔状態と全身状態の関連性を評価し、必要に応じて医師への報告を行います。
リハビリ専門職は、咀嚼・嚥下機能の訓練を通じて食事動作の改善に貢献。
ケアマネジャーは、評価結果を踏まえてケアプランの見直しを検討し、他のサービス事業所との情報共有を図ります。
歯科医師・歯科衛生士は、専門的な立場から助言や指導を提供し、必要に応じて歯科医療を提供。
このように、多職種がそれぞれの専門性を発揮し、情報を共有しながら連携することが、制度の効果を最大限に引き出すポイントとなります。
ご家族に対しても、評価結果と今後のケア方針について丁寧に説明し、在宅での口腔ケアへの協力を求めることが大切です。
当サイト内では口腔ケアに関する加算について、以下も掲載しています。参考にしてください。
・口腔衛生管理加算とは?算定要件、単位数、対象サービスなどまとめ
・口腔・栄養スクリーニング加算とは?算定要件、単位数や注意点について分かりやすく解説
・経口維持加算とは?算定要件・単位数や対象者、算定のポイントなど解説
厚生労働省リーフレットの活用法
厚生労働省は、口腔連携強化加算の周知と現場での活用を目的に、わかりやすいリーフレットを公開しています。
この資料は制度の要点を簡潔にまとめており、職員研修やご利用者・ご家族への説明にも役立つでしょう。
リーフレットは以下よりダウンロードできます。
介護保険最新情報 Vol.1344 令和7年1月10日 厚生労働省老健局老人保健課「口腔連携強化加算に係るリーフレットについて」
まとめ
口腔連携強化加算は、令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で新設された制度です。
訪問介護や訪問看護、短期入所など複数のサービスで算定でき、月1回50単位が加算されます。
ご利用者の口腔状態を評価し、歯科医療機関やケアマネジャーへ情報を提供することが要件となります。
この制度の活用により、咀嚼や嚥下機能の維持、誤嚥性肺炎や低栄養の予防が期待できます。
届出手続きや評価記録、併算定制限など、現場で注意すべきポイントも少なくありませんが、加算に取り組むことで、ご利用者の生活の質向上と健康維持に大きな効果が期待できます。
ご利用者の笑顔と健康を支えるため、口腔連携強化加算を有効活用し、質の高い介護サービスの提供を目指しましょう。
この記事の執筆者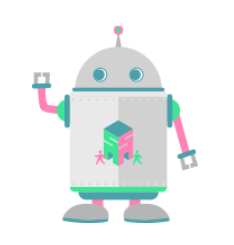 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。





















