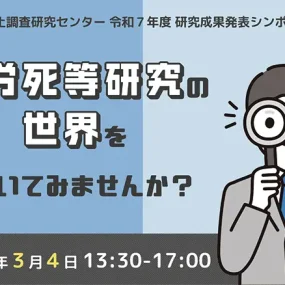「夜勤中に強い眠気に襲われて仕事に集中できない」
「夜勤明けに布団に入っても全然眠れない」
「日勤に戻っても体調がなかなか戻らない」
夜勤やシフト勤務をされている皆さんの中には、このような睡眠のお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
これらの症状は単なる気持ちの問題や疲労によるものではなく、交代勤務睡眠障害(SWD)という睡眠時のトラブルを抱えている可能性があります。
夜勤勤務者の約2~3割がこの障害に該当するとの報告もあり1)、決して珍しいことではありません。
睡眠の質が低下すると、日中の眠気や疲労感に悩まされるだけでなく、注意力の散漫や判断力の低下を招き、仕事上のミスや事故につながる危険性があります。
本記事では、交代勤務睡眠障害の症状や原因を詳しく解説し、今日からできる具体的な対策をお伝えします。
介護の現場において夜勤で働く皆さんが少しでも楽に、健康に過ごせるよう、実践的な情報をまとめました。
目次
交代勤務睡眠障害(SWD)とは

交代勤務睡眠障害(SWD)は、夜勤や不規則な交代制勤務によって身体の生体リズムが乱れ、その結果として睡眠困難や過度の眠気が生じる睡眠障害です2)。
人間の身体には約24時間周期の体内時計が備わっており、通常は夜間に眠り、日中に活動するよう調整されています。
SWDでは、勤務時間が本来の睡眠時間に重なるために、眠りたいときに眠れない、起きていたいときに強い眠気に襲われるという状態になります2)。
これらの症状は交代勤務の期間に限って持続し、通常の昼間勤務の生活に戻れば改善する傾向がみられます2)。
一般的な不眠症との違い
SWDは医学的に概日リズム睡眠覚醒障害群という睡眠障害に分類されます2)。
勤務スケジュールによって睡眠時間帯が大きくずれることが主な原因となる点で、ストレスや精神的要因で生じる一般的な不眠症とは異なる病態です。
一般的な不眠症が心理的ストレスや精神的な要因で起こることが多いのに対し、SWDは体内時計と勤務時間のずれという物理的な要因が根本原因となります。
そのため、通常の不眠症の治療法では十分な効果が得られないことがあり、勤務パターンに応じて対策が必要になります。
交代勤務睡眠障害(SWD)の主な症状

交代勤務睡眠障害は、睡眠そのものの問題だけでなく、身体や精神面にもさまざまな影響を及ぼします。
ここでは、SWDによって現れる具体的な症状を、
・睡眠に関するもの
・身体への影響
・精神的な影響
の3つに分けて詳しく見ていきましょう。
睡眠に関する症状
SWDになると、まず現れるのが勤務中の強い眠気と、眠りたい時間に眠れないという症状です2)。
夜勤の途中や深夜から朝方にかけて、どうしようもないほどの眠気に襲われ、気がつくと居眠りしてしまいそうになることがあります。
夜勤で働く方の睡眠時間は、日勤の方と比べて1~4時間ほど短くなってしまうことがわかっています2)。
また夜勤が終わって昼間に家で寝ようとしても、なかなか寝付けません。やっと眠れても眠りが浅く、途中で何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠った感じがしないまま次の勤務を迎えることになります。
こうした睡眠不足と眠気が続くと、仕事に集中できなくなったり、判断を間違えたり、ミスが増えたりする問題が起こります2)。
こうしたことで、夜勤後に車で帰宅する時の居眠り運転や事故のリスクが高くなることも知られています2)。
身体への影響
SWDは、長い目で見ると身体の健康にも様々な問題を引き起こす可能性があります。睡眠不足が続いたり体内時計が乱れたりすることで、生活習慣病にかかりやすくなってしまいます。
ある研究では、夜勤で働く方は普通の日勤の方と比べて、心筋梗塞や脳卒中などの心臓や血管の病気になる確率が約1.2倍高くなることがわかっています3)。
夜勤の回数が多いほど、肥満や高血圧、糖尿病になりやすく、それが原因で血管が硬くなる病気につながることも多いとされています。
さらに世界保健機関の関連機関では、夜勤の仕事を発がんの可能性があるものとして分類しています4)。
これは夜勤が乳がんなどの一部のがんのリスクを高める可能性があるという研究結果に基づいています。
精神的な影響
SWDは心の健康にも影響します。夜勤が続いて十分な睡眠が取れない状態が続くと、脳も十分に休めずストレスに弱くなり、気分が落ち込んだりイライラしたりすることが多くなります。
実際に、夜勤で働く方は日勤の方と比べて、うつ病や不安障害になりやすいという研究報告があります5)。
特にSWDになっている方では、忙しい勤務の中で気持ちが沈んだり、人と関わるのが面倒になったりすることが多く見られます2)。
交代勤務睡眠障害(SWD)のセルフチェック
ご自身がSWDに当てはまるかどうか、簡単にチェックしてみましょう。
・夜勤中など本来起きているべき時間に強い眠気に襲われることが頻繁にある
・眠るべき時間にベッドに入ってもなかなか眠れない、熟睡できない
・常に睡眠不足や疲労感が抜けない状態が続いている
上記の症状が3ヶ月以上続き、日常生活に支障を来している場合、SWDの可能性があります。
より詳しいセルフチェック項目や具体的な睡眠のコツについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
交代勤務睡眠障害(SWD)が起こる原因とメカニズム
なぜ夜勤や交代勤務で睡眠の問題が起こってしまうのでしょうか。
SWDには、主に3つの原因が関わっています。
最も根本的な原因は体内時計のずれですが、それに加えて睡眠ホルモンの分泌異常、さらには睡眠時間の不足や精神的ストレスといった要因も重なり合って症状を悪化させています。
ここでは、これらの原因について詳しく解説していきます。
体内時計(概日リズム)の乱れ
SWDの根本原因は、体内時計(概日リズム)の乱れにあります。
私たち人間の身体には約24時間周期の体内時計が備わっており、通常は朝に目覚めて日中に活動し、夜になると眠くなるように調整されています。
この体内時計は脳内の視交叉上核という部位で管理され、朝の太陽光や規則的な生活習慣によって毎日リセットされる仕組みです。
しかし夜勤や不規則な交代勤務では、この体内時計に逆らって生活せざるを得ないため、生体リズムに大きなズレが生じます6)。
例えば夜勤では夜間に強い光を浴びて活動し、昼間に寝る生活になりますが、身体はすぐには新しいリズムに順応できません。
その結果、身体は眠りたがっているのに起きて仕事をしなければならない、身体は本当は目覚めて活動したい時間に眠らなければならないという状態が続き、睡眠と覚醒のタイミングが体内時計と噛み合わなくなってしまうのです6)。
メラトニン分泌の乱れ
夜勤中は仕事の緊張や照明による刺激などで交感神経が優位になり、睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンの分泌サイクルにも乱れが生じます。
通常、メラトニンは夜暗くなると脳の松果体から分泌が増え、私たちに自然な眠気をもたらしてくれます。
しかし、夜勤では一晩中人工的な明るい光の下で過ごすため、夜間にメラトニンが十分分泌されず抑制されてしまうことがわかっています7)。
その結果、勤務が終わって朝に帰宅してもすぐには眠くならず、むしろ昼近くになってようやく眠気が出てくるという状況になりがちです。
その他の要因
体内時計の乱れ以外にも、SWDにはいくつかの要因があります。
まず大きな問題となるのが慢性的な睡眠時間の不足です。
夜勤や交代勤務ではどうしても寝る時間と起きる時間が不規則になるため、結果的に総睡眠時間が不足しやすくなります。
また、夜勤そのものが心身にストレスを与えることも重要な要因です。
外が暗い真夜中に働くこと自体が身体に大きな負荷や緊張をかける上、家族や友人とは生活時間が合わず孤独感や精神的ストレスを感じることもあります。
交代勤務睡眠障害への予防対策(セルフケア)

交代勤務や夜勤による睡眠の問題を改善するには、日頃のセルフケアが非常に重要です。
体内時計の乱れを最小限に抑え、少しでも質の良い睡眠を確保するために、具体的にできる対策があります。
ここでは、今日からでも始められる実践的な方法を4つのポイントに分けてご紹介します。
完璧にすべてを実行する必要はありません。ご自身の生活スタイルや勤務パターンに合わせて、できるものから取り入れてみてください。
睡眠環境を整える
まず基本となるのは、眠るための環境づくりです。夜勤明けなど昼間に睡眠をとる際には、夜間の就寝と同じくらい静かで暗い寝室環境を整えるよう心がけましょう。
具体的には、カーテンは遮光性能の高いものに替えて日中の強い日差しを遮り、就寝時には部屋をできるだけ暗くします8)。耳栓やアイマスクを利用しても良いでしょう。
また寝室の位置も可能であれば窓から離れた静かな部屋を選び、室内の温度・湿度も快適に感じられる範囲に調整してください8)。
ご家族と同居している場合は、昼間に睡眠をとる旨を伝えて協力してもらい、インターホンの音や生活音にも配慮してもらえるようにしましょう。
就寝前にはスマートフォンやパソコンの画面など明るい光を見ることも極力避け、軽いストレッチやぬるめの入浴などでリラックスしてスムーズに入眠できるよう整えてみましょう。
食事のタイミングと内容を工夫する
交代勤務では食事のとり方も睡眠に影響します。夜勤中の食事は眠気対策として適度に摂ることが大切です。
深夜に空腹だと余計に眠くなってしまうため、エネルギー補給に軽食をとるのは有効ですが、脂っこい食事や甘い菓子類は血糖値の乱高下を招き眠気を悪化させる可能性があります。
夜勤中は消化に良い軽い食事であるおにぎりやサンドイッチ、スープや、適量のタンパク質を含む食品で栄養補給しつつ、水分もこまめに取りましょう。
一方、勤務後の食事にも工夫が必要です。
朝方に勤務を終えてすぐ大量に食事をすると、消化活動が活発になって交感神経が刺激され、眠気が吹き飛んでしまう恐れがあります。就寝直前の重い食事やカフェイン摂取は避けるのが鉄則です8)。
また、規則正しい食習慣は体内時計を整える助けになります。特に、朝食を毎日しっかり摂ることは重要です8)。
仮眠を効果的に取る
仮眠の活用は交代勤務者にとって強力な眠気対策になります。
勤務中や勤務前後に上手に仮眠を取ることで、睡眠不足を補い、仕事中のパフォーマンス低下を防ぐことができます8)。
ポイントは短時間とタイミングです。可能であれば夜勤シフトの最中に1回、20~30分程度の仮眠時間を確保してみましょう。
特に深夜0時から明け方4時の時間帯に20~30分程度の仮眠を取ると、眠気や疲労感の軽減に効果があると報告されています8)。
一方で、長すぎる仮眠は目覚めた直後に頭がぼんやりしてしまい、かえって作業効率が低下したとの研究もあります8)。
眠り込んでしまわないよう、仮眠時間は長くても1時間以内、できれば30分前後に収め、目覚まし時計をセットしておくと良いでしょう。
仮眠の効果を高めるテクニックとして注目されているのがカフェインナップです。
これは、仮眠を始める直前にコーヒーなどでカフェインを摂取し、すぐ短時間の仮眠に入る方法です。
摂取したカフェインが効き始めるまでおよそ20~30分かかるため、その間仮眠をとって目覚めるころにちょうど覚醒効果が現れ、寝起きのだるさを軽減できるとされています8)。
生活リズムを調整する
夜勤や交代制勤務と上手に付き合うには、勤務パターンに応じた生活リズムの調整も大切です。
夜勤の頻度によって、体内時計への対策法を変える必要があります。
例えば週に1~2回程度しか夜勤がない場合、体内時計を大きく夜型に変えてしまわないようにする方法があります。
夜勤明けの日でも朝にしっかり日光を浴び、日中は無理に長く寝過ぎず普段の昼型の生活リズムを保ち、夜にまとめて睡眠をとるようにする方法です。
一方、夜勤が連続して続く勤務体系のときは、日勤に合わせた生活リズムを維持しようとすると、かえって睡眠不足が深刻になる可能性もあり注意が必要です8)。
この場合、逆に夜勤のリズムにある程度身体を適応させる方が楽になることもあります。
医療機関での交代勤務睡眠障害の治療について
セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合は、医療機関での専門的な治療を検討することも大切です。
受診すべき診療科
セルフケアを行ってもなお睡眠障害が深刻な場合や、日常生活に支障を来すほど症状が続く場合は、医療機関での専門家への相談を検討しましょう。
SWDが疑われるとき、受診先としては睡眠医療の専門外来がおすすめです。
日本では、睡眠障害は主に精神科や心療内科の分野で扱われることが多く、大病院では睡眠外来や不眠症外来など専門外来が設置されている場合もあります。
主な治療方法
まずは睡眠環境について実態を確認して、その後治療を決めていくという流れが一般的です。
夜勤前の仮眠や夜勤明けの食事のタイミングなど、実際の勤務スケジュールを踏まえた具体的な方法についても相談する方が多く見られます。
体内時計を調整するために、明るい光を浴びるタイミングを工夫する光療法という方法もあります。
夜勤前や夜勤明けの光の当たり方など、働きながら取り入れやすい方法を検討していくことになります。
症状の程度によっては、内服薬による治療も考慮される場合があります。夜勤による睡眠の悩みでお困りの場合は、専門医への相談を検討してみてください。
まとめ
交代勤務睡眠障害は、夜勤や不規則なシフト勤務によって体内時計が乱れることで起こる睡眠障害です。
勤務中の強い眠気や不眠に悩まされるだけでなく、長期的には生活習慣病のリスク増大やメンタルヘルスへの影響などを引き起こし、軽視できない問題があります。
しかし、睡眠環境を整えたり、仮眠を上手に活用したり、食事のタイミングを工夫するなど、日常でできるセルフケアで症状を和らげることは可能です。
セルフケアでも改善が難しい場合は、専門医への相談を検討してみてください。
医療機関で適切な治療を受けることで、このような睡眠の問題にも対処できるようになるかと思います。
夜勤は身体的・精神的に負担の大きい働き方です。
それでも、睡眠に関する正しい知識を持ち、できることから少しずつ対策を始めることで、その負担を減らせるよう心がけていきましょう。
今日からできるセルフケアを取り入れて、夜勤と上手に付き合いながら、心身ともに健康な毎日を目指していきませんか。
質の高い睡眠を取るコツなどを以下の記事でまとめていますので、合わせて参考にしてください。
・【医師執筆】夜勤・交代勤務者の睡眠のコツ|不規則シフトでの睡眠の質向上のコツとは
1. Pallesen S, et.al. Prevalence of Shift Work Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Psychol. 2021;12:638252.
2. American Academy of Sleep Medicine. The International Classification of Sleep Disorders – Third Edition (ICSD-3). Darien, IL: AASM; 2014.
3. Vyas MV, et al. Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012;345:e4800.
4. Erren TC, et al. IARC 2019: “Night shift work” is probably carcinogenic: What about disturbed chronobiology in all walks of life? J Occup Med Toxicol. 2019;14:29.
5. Kalmbach DA, et al. Shift Work Disorder, Depression, and Anxiety in the Transition to Rotating Shifts: The Role of Sleep Reactivity. Sleep Med. 2015;16(12):1532-1538.
6. 藤原広明・藤木通弘. 交代制勤務と睡眠. 公衆衛生. 2022;86(1):28-34.
7. Wickwire EM, et.al. Shift Work and Shift Work Sleep Disorder: Clinical and Organizational Perspectives. Chest. 201;151:1156-1172.
8. 厚生労働省 睡眠指針検討会. 健康づくりのための睡眠指針 2023(案)第3回検討会 資料. 2023.
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
| この記事の執筆者 | 廣瀬 正和 関西の国立大学医学部を卒業後、大学病院勤務を経て市中病院で脳神経内科医として臨床経験を積みました。現在は母校の大学院医学研究科で、MRIやPETなどの脳画像データと機械学習を組み合わせた神経変性疾患の早期診断マーカー開発の研究に従事しながら、外来診療も継続しています。 神経内科専門医として睡眠障害の診療に携わる一方、自身も医師として夜間当直や不規則勤務を経験してきたことで、医療従事者が抱える睡眠問題の深刻さを身をもって理解しています。 臨床と研究、そして自身の体験を踏まえた実践的な知見をお届けします。 【専門資格】医師免許/総合内科専門医/神経内科専門医/脳卒中専門医/認知症専門医・指導医 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。