介護施設では、ご利用者の安全を守るためのリスクマネジメントが欠かせません。
2021年4月の介護報酬改定により「安全対策担当者」の選任が義務化され、施設内のリスク管理や事故防止対策が強化されることになりました。
本記事では、安全対策担当者の設置義務化の背景、役割や必要な研修、関連する加算・減算などについて解説します。
介護現場の安全性向上と、ご利用者へのより良いサービス提供のために、ぜひ最後までお読みください。
目次
安全対策担当者とは

安全対策担当者とは、介護施設において安全対策の中心的な役割を担う専任の職員のことです。事故防止や再発防止、発生時の適切な対応(リスクマネジメント)を推進する役割を担います。
安全対策担当者は介護事故やヒヤリハット事例の収集・分析、再発防止策の検討、PDCA(plan:計画→do:実行→check:評価→act:改善)サイクルを回し、施設全体の安全管理体制の構築を担当します。
「専任」とは、その業務を主に任されていることを意味し、他の業務との兼任も可能ですが、安全対策業務に支障がない範囲に限られます。
例えば、フロアリーダーが安全対策担当者を兼任する場合、リーダー業務が忙しすぎて安全対策業務が疎かになるようでは、専任とは言えません。
後ほど記載しますが、介護報酬で「安全対策体制加算」も新設されるなど、介護施設の安全対策体制の強化が推進されています。非常に重要な役割を持つ人物だといえるでしょう。
安全対策担当者の設置が義務化された背景
安全対策担当者が義務化された背景には、介護現場での事故やトラブルの増加があり、かつ介護施設における事故防止への取り組みにばらつきがあったことが挙げられます。
厚生労働省の調査(2018年)によると、特別養護老人ホームの54.1%のみが安全対策担当者を設置しており、約半数が未対応でした。特に注目すべきは「事故防止のための指針」の整備状況で、定期的に見直しを実施していた施設は21%に留まり、21.3%の施設が全く見直しを行っていませんでした。
参照:介護老人福祉施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業
また、近年の介護現場ではICT化が進み、見守りセンサーやカメラなどの新たな技術が導入されています。
こうした環境変化に対応した安全対策の見直しや、スタッフへの教育も必要となっています。そのため、マニュアル体制を再整備するといったことなども、安全面から重要性が増しています。
このような状況を踏まえ、厚生労働省は2021年4月の介護報酬改定で、施設系サービスのすべてにおいて安全対策担当者の選任を義務化しました。これには6ヶ月の経過措置期間が設けられ、2021年9月末までに対応することが求められました。
安全対策担当者の主な役割
安全対策担当者は、介護施設内の安全管理と事故防止を推進する責任者です。具体的な役割は以下の通りです。
安全対策委員会の運営とリスク管理の推進
・安全対策委員会を定期的に開催し、多職種連携でリスク管理の検討や改善案を協議します。
・委員会を通じて事故の予防策を具体化し、施設内の安全対策の方針を策定・決定します。
・委員会の運営を通じ、組織全体の安全対策レベル向上を目指します。
職員への安全教育・研修の実施
・新任職員へのオリエンテーションを実施し、介護現場のリスク管理や安全対策の基本を教育します。
・既存職員に対しても定期的な研修を行い、安全管理意識を高め、施設全体の安全文化を醸成します。
・転倒防止対策、誤薬防止策、食事介助の際の注意点など、具体的かつ実践的な教育を提供します。
事故防止のためのマニュアル作成と更新
・過去の事故やヒヤリ・ハット事例を収集・分析し、具体的な事故防止マニュアルを整備します。
・作成したマニュアルは定期的に見直し、最新の状況に合わせて改善します。
・マニュアルを施設全職員へ周知し、緊急時にも迅速で的確な対応が取れるよう準備を整えます。
事故発生時の対応・再発防止策の策定
・万が一事故が発生した際は迅速に状況を把握し、原因の分析・究明を行います。
・同様の事故を防ぐための再発防止策を策定し、職員全員に共有・徹底を図ります。
・必要に応じて、事故報告書の作成と行政機関への報告を行います。
日常的なリスクアセスメントの実施
・定期的に施設内を巡回し、リスクや危険要素を早期に発見・評価します。
・発見したリスクに対し、職員や管理者と協力して迅速に対処します。
・リスク管理の結果を記録・分析し、継続的な改善活動を行います。
外部研修の受講と最新情報の取得・共有
・定期的に外部研修に参加し、リスクマネジメントや安全対策に関する最新知識・技術を習得します。
・研修で得た情報を施設内で共有し、最新の知識を施設運営に反映させます。
安全対策担当者の選定ポイント

安全対策担当者として、どのような人材を選定すべきでしょうか。
資格要件は特に定められていませんが、介護現場での経験があり、施設の状況をよく理解している人材が望ましいでしょう。
求められる資質や経験
安全対策担当者には以下のような資質や経験が求められます。
・リスク管理に関する基本的な知識
・施設全体を見渡せる広い視野
・スタッフからの信頼
・情報を整理・分析する能力
・マニュアル作成や研修実施のスキル
兼任は可能か
安全対策担当者は「専任」とされていますが、これは他の業務と兼任できないという意味ではありません。専任とは「専らその業務を任される」という意味であり、安全対策業務に支障がなければ、他の業務と兼任することも可能です。
ただし、リーダー業務などで多忙な場合、安全対策業務が疎かになる可能性があるため、業務量のバランスを考慮する必要があります。
兼任可能な例
・介護職員と安全対策担当者
・生活相談員と安全対策担当者
・看護職員と安全対策担当者 など
兼任の際の注意点
・安全対策業務に十分な時間を確保できること
・兼任する業務が過重にならないよう配慮すること
・安全対策業務が疎かにならないよう業務分担を明確にすること
安全対策担当者に必要な研修
安全対策担当者には、外部研修の受講が求められています。この外部研修は安全対策体制加算の算定要件にもなっているため、重要な要素です。
安全対策担当者は、外部の専門的な研修を受けることで、リスクマネジメントに関する知識を深め、自施設での安全対策の質を高めることが期待されています。
外部研修では、最新の事故防止の考え方や手法、他施設の取り組み事例なども学ぶことができるため、自施設の安全対策の向上に役立つでしょう。
安全対策担当者向けの研修
安全対策担当者向けの研修としては、以下のような団体が実施するものがあります。
・公益社団法人全国老人福祉施設協議会
・公益社団法人全国老人保健施設協会
・全国社会福祉法人経営者協議会
・各都道府県の介護関連団体が実施する研修
・ 外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、 施設のマネジメント等の内容を含むものであり、関係団体(公益社団法人全国老人福祉施 設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等)等 が開催する研修を想定している。
安全対策担当者が関連する加算・減算について
安全対策担当者の設置に関連する加算として、「安全対策体制加算」があります。
この加算を算定することで、施設の収益アップにもつながります。また、介護施設における安全対策の強化を促進する重要な仕組みともなっています。
他に、減算のリスクとして「安全管理体制未実施減算」があります。
安全対策体制加算の概要
安全対策体制加算は、2021年度の介護報酬改定で新設された加算で、介護施設における事故防止の取り組みを評価するものです。
対象となるのは以下のサービスです。
・介護老人福祉施設(特養)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
加算取得は施設にとって収入増加だけではなく、施設全体の安全文化の醸成にもつながる重要な取り組みと言えるでしょう。
安全対策体制加算について、詳細は以下の記事をご覧ください。
安全管理体制未実施減算の概要
安全対策担当者を選任していない、あるいは必要な研修やマニュアル整備が不十分な場合には、安全管理体制未実施減算の対象となり、1日あたりの介護報酬が減額される可能性があります。
このため、施設運営者は安全対策担当者の設置・育成に注力し、加算取得を目指すことが経営改善にもつながると考えられています。
安全管理体制未実施減算について、詳細は以下の記事をご覧ください。
まとめ
安全対策担当者は、介護施設における安全対策の要となる重要な役割を果たします。2021年度の介護報酬改定により設置が義務化されたことで、その重要性はさらに高まっています。
安全対策担当者の主な役割は以下です。
・安全対策委員会の運営とリスク管理の推進
・職員への安全教育・研修の実施
・事故防止のためのマニュアル作成と更新
・事故発生時の対応・再発防止策の策定
・日常的なリスクアセスメントの実施
・外部研修の受講と最新情報の取得・共有
また、安全対策体制加算の算定には、安全対策担当者を設置し外部研修を受け、組織的に安全対策を実施する体制を備えることが必須となっています。
適切な人材を選び、必要な研修を受講させることで、施設の安全対策の質を高めるとともに、加算による収益アップも期待できます。
安全対策は担当者一人の努力だけでは十分な効果を上げることはできません。組織全体で安全意識を高め、PDCAサイクルを回し続けることが、ご利用者の安全を守り、質の高い介護サービスを提供するための鍵となります。
この記事の執筆者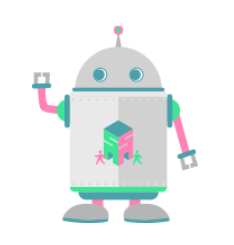 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。





















