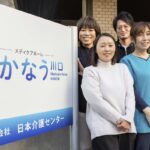介護の現場では、以前から腰痛の問題が深刻化しており、複数の調査研究にて介護職員の半数以上、高い場合は9割近く介護職員の高い腰痛発生率が報告されています。
また、腰痛が発症する原因として移乗動作時が最も多く、支援によって介助者が要介護者の持ち上げる動作にて起こっていることが指摘されています。
厚生労働省では、2013年に「職場における腰痛予防対策指針」を改定するなど対応を行っています。
その中には、ボディメカニクスに関する内容やノーリフティングケアに関する内容が多く記載されており、介護事業所では職員の腰痛の予防のために対策を講じることが求められています。
腰痛による離職、といったケースも中にはあります。また、腰痛が発症してしまうと介護業務に支障をきたすでしょう。そのため、腰痛予防・対策は介護施設にとって非常に重要な施策といえます。
本記事ではボディメカニクスの8原則やその活用例に焦点を当てて、介護職員の腰痛予防を図る方法をご紹介していきます。腰痛に悩む介護職の方はぜひ参考にしてください。
参考:厚生労働省職場における腰痛予防対策指針
目次
ボディメカニクスとは

ボディメカニクスとは、
解剖学、生理学、力学などの基礎知識を活用することにより、身体の機能や構造と身体運動がどのように関連しているか、その仕組みについてよりよく理解しようとする応用理論
のことです。
介護では、移乗動作のような身体を動かす作業姿勢と、食事介助のような基本的な姿勢は同じままで行う作業姿勢に分かれます。
ボディメカニクスを理解し、介護に活用することで、最小の労力で介護を行うことができ、職員の腰痛予防などにも効果的と言われています。
ボディメカニクスは要介護者・介護者の双方にメリットがある介護技術

腰痛に悩む介護職は多いです。職員の腰痛をいかに予防するかは、介護施設が取り組むべき問題ともいえるでしょう。
ボディメカニクスは、要介護者および介護者の双方にメリットがある介護技術です。その理由を解説します。
介護者の身体的負担が軽減される
ボディメカニクスを活用した介護を実践することで、力任せの介助ではなく、最小限の力での介助を行うことができます。
そのため、介護者に起こりやすい腰痛などの痛みの予防など、身体的負担に繋げることが期待されます。
今後、介護職員の高齢化という課題もありますが、ボディメカニクスを活用することで、年齢が高くなったとしても無理なく介護業務を続けることや、離職等の予防に繋がることも考えられます。
要介護者の身体的負担が軽減される
力任せの介助では、身体の内出血や、身体の緊張の高まりが生じやすくなります。
ボディメカニクスを活用した介護では力任せの介助を受けることが少なくなり、要介護者の身体的な負担の軽減にも繋がることが期待されます。
介護者・要介護者の心理的負担が軽減される
ボディメカニクスを活用した介助では、正しい姿勢や技術を活用して介護を行うため、姿勢の安定やスムーズな動作が可能になります。
被介護者はケガや転倒の心配をせずに安心した介助を受けることができます。
また、介護者および要介護者が最小限の力の発揮で介助を行うことができるため、介護者・要介護者ともに楽であり、安心感に繋がります。
そういった安心感から、介護者と要介護者との信頼関係に結びつくこともあります。
ボディメカニクス基本の8原則
ボディメカニクスには基本となる8原則があります。それぞれの原則について解説します。
支持基底面を広くする
支持基底面とは体重を支えるために床と接している面積のことです。
支持基底面は広いほど身体が安定するため、両足を肩幅ぐらいに広げたり、片方の足を斜め前に出し前後へのバランスをとりやすくすることで、足を閉じている(=支持基底面が狭い)時に比べて、身体が安定します。
また、ご利用者の移乗支援など重心移動を伴う支援の際には、力を入れて踏ん張ったとしてもバランスが崩れにくくなります。
重心を低くし骨盤を安定させる
介助する際には、支持基底面を広くすることに加え、重心を低くすることもよりバランスを保つためには重要となります。
具体的には、膝を曲げるなど、重心を下げることで腰への負担を少なくし、介護者をしっかりと支えることができます。
要介護者との重心を近づける
介助の際に、介護者と要介護者とで身体を近付けることで、重心が近づき、力が入りやすくなります。
余計な力を使うことがなく、要介護者へも力が伝わりやすいため、最小限の力で介助が可能です。要介護者の負担の軽減にも繋がります。
要介護者の身体をねじらず小さくまとめる
介助の際に要介護者が手足を伸ばすような姿勢では、体重が各部位に分散されてしまいます。そのため、腕を胸の上にのせる、膝を立てていただくなど、身体をコンパクトにまとめていただくと、介助がしやすくなります。
また、要介護者の腕や足を組んでいただくことで、身体とベッドなどの接地面との摩擦が少なくなり、移動の負担が軽減されます。
身体全体を利用し大きな筋肉を使う
移乗や移動などの介助の際には、手や腕などの一部分の筋群だけに力の発揮に集中させてしまうことがあります。
その場合、一部の筋肉への負担が大きく、介護者の手首の痛みなどに繋がる恐れがあります。
大きな筋群(腹筋や背筋、太ももやお尻の筋肉など)を同時に使用することで、一つの筋肉にかかる負担を少なくし、効率的に支援や作業を行うことができます。
持ち上げずに水平移動を行う
ベッド上での移動支援の場合においては、介護者の身体を持ち上げようとすると、介護者の腰や手首などへ負担が生じやすくなります。
そのため、介護者が横に滑るように水平移動を行うことで、重力の抵抗を受けにくく、小さな力で移動支援を行うことができます。
身体を押さずに手前に引く
押す力は腕の力を多く使いますが、引く力の方が身体全体の筋肉を使うとされています。加えて、引く力は介護者の重心移動も上手く活用すると、筋肉にかかる負担を少なくすることもできます。
また、押す動作にて介護者と要介護者との距離が遠くなり、要介護者への不安感を強くする恐れがあります。引く動作で、介護者と要介護者との距離を近付けることで、互いに安心感に繋がります。
テコの原理を利用する
支えとなる部分(支点)、力を入れる部分(力点)、加えた力が働く部分(作用点)の関係を前提に支援することで、少ない力で大きな効果を得ることができます。
自身より身体の大きい要介護者であっても、要介護者の膝や肘、お尻などを支点にして、遠心力を利用することで、小さな力で起き上がるよう介助することができます。
ボディメカニクスを行う際の注意点

介護場面でボディメカニクスを活用するためには、以下の点に注意しましょう。
要介護者に声をかけながら行う
ボディメカニクスに関わらず、介助をする際には要介護者へ声掛けを行い、同意を得てから行うようにしましょう。
同意が得られていない中での介助は、嫌がられたり、介護者・要介護者の互いに余計な力が必要となってしまう恐れがあります。
しっかりと同意を得て次の動作を理解いただくことで、互いに安心感に繋がります。また、要介護者を尊重することで、信頼感にもつながるでしょう。
要介護者にできることはしてもらう
ボディメカニクスを理解した支援を行う上でも、ご利用者のADLの維持や、介護者が必要以上に力を入れてしまわないように、ご利用者にもできることはしていただく必要があります。
例えば移乗動作では、全てがご自身で行うことが難しくても、
・手すりを持ってもらう
・立ち上がるためにおじぎをしてもらう
・立ち上がる際に踏ん張ってもらう
など、部分的にいずれかの動作を行っていただくことで、介助は幾分か楽になることでしょう。
また、ご利用者に少しでも力を発揮していただくことで、ADLの維持に繋がり、長期的に考えてもご利用者に、元気に健康で過ごしていただくことにも繋がっていきます。
ボディメカニクスの活用シーン

実際の介護の場面で、どのようにボディメカニクスを活用するか、以下の例もご参照ください。
起き上がるとき
ベッドからの起き上がり動作のときには、
・支持基底面を広くする
・重心を低くし骨盤を安定させる
・要介護者の身体をねじらず小さくまとめる
・要介護者との重心を近づける
・テコの原理を利用する
が活用できます。
起き上がり介助を行う準備として、介助者の身体を支えるために足幅を広げ支持基底面を広くし、ベッドの高さに合わせて腰を曲げるのではなく、膝や股関節を曲げて重心を低くして骨盤を安定させる姿勢をとります。
要介護者には起き上がり動作を行っていただくため、膝を立ててもらう、両腕は胸の前に組んでもらうなど、体をなるべく小さくまとめてもらいます。
また、可能であればお腹を見るように頭を起こし、背中を丸めてもらうことも効果的です。
起き上がり支援を行うために、介護者の腕を首や肩甲帯周囲と膝の下を支えながら、要介護者との重心を近づけます。
要介護者のお尻を支点として、てこの原理を利用しながら起き上がり動作の介助を行います。
体の向きを変えるとき
ベッド上での寝返り動作支援など、要介護者の体の向きを変えるときには、
・支持基底面を広くする
・重心を低くし骨盤を安定させる
・要介護者の身体をねじらず小さくまとめる
・身体を押さずに手前に引く
が活用できます。
起き上がり動作のときと同じく、準備として支持基底面を広くし、ベッドの高さに合わせて腰を曲げるのではなく、膝や股関節を曲げて重心を低くして骨盤を安定させる姿勢をとります。
また、膝を立ててもらう、両腕は胸の前で組んでもらうなど、体を小さくまとめてもらいます。
寝返るように体の向きを変えていただく際には、要介護者の向いていただきたい方向に介助者は立ち、押すのではなく手前に引くように寝返り支援を行います。
立ち上がるとき
要介護者の立ち上がりを支援するときには、
・支持基底面を広くする
・重心を低くし骨盤を安定させる
・要介護者との重心を近づける
・身体全体を利用し大きな筋肉を使う
が活用できます。
立ち上がり支援でも、足を広げるなど支持基底面を広げることや重心を低くすることで、万が一、支援中に要介護者がふらついた際にも、対応できるようにバランスを取ることができます。
立ち上がりを支援する際には、要介護者を上に引き上げるように支援するのではなく、介護者自身も腰を落として重心を低くしながら、一緒に立ち上がるように支援することがポイントです。
要介護者が立ち上がる際に、重心を移動させるためにお辞儀をしてもらいます。
お辞儀をしてもらうことで、要介護者のお尻から足元へ重心が移動するだけでなく、介助者との重心が近づき、お互いの負担の軽減に繋がります。
また、重心を低くして一緒に立ち上がろうとすることで、腕などの一部分だけでなく、足腰の筋肉を含めた身体全体を利用して支援を行うことができます。
座るとき
要介護者が座る(着座する)ときは、
・支持基底面を広くする
・要介護者との重心を近づける
が活用できます。
立ち上がり支援同様に、介助者は足を広げるなど支持基底面を広げることで、安定感につながります。
また、互いの体を近づけて、一緒に腰を落とすように支援することがポイントです。体を近づけることで、互いの重心も近づき、要介護者へ力が伝わりやすくなります。
勢いよく座ってしまうと、骨折などの外傷のリスクが高まります。力が伝わりやすいと、座る速度も調整しやすく、ゆっくりと座っていただくことにも繋がります。
物品の持ち運び
物品の持ち運びのときは、
・支持基底面を広くする
・重心を低くし骨盤を安定させる
・身体全体を利用し大きな筋肉を使う
・持ち上げずに水平移動を行う
が活用できます。
物品を持つ/持ち上げる際にも、支持基底面を広くすることや、重心を低くすることでバランスをとることは重要です。
また、物品を持ち上げる時なども、腕の力だけで持ち上げようとするのではなく、腰を落とした状態で物品を抱え、足の力を利用して立ち上がるようにしましょう。
身体全体、特にお尻や太ももなど足の大きな筋肉を用いるようにすることで、体にかかる負担を少なくすることができます。
また、物品を持ち上げる必要がない場合、なるべく水平移動させることで物品にかかる重力の影響を少なく移動させることができます。
ボディメカニクス以外での腰痛予防対策

厚生労働省が発出している「職場における腰痛予防対策指針 」にて、人力による重量物の取扱いとして、
・人力による重量物取扱い作業が残る場合には、作業速度、取扱い物の重量の調整等により、腰部に負担がかからないようにすること。
・満 18 歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね 40%以下となるように努めること。満 18 歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の 60%位までとすること。
とされています。
つまり、
・体重が50kgの男性介助者⇒持ち上げる重量を20kg以下(体重50kgの40%以下)
・体重が50kgの女性介助者⇒持ち上げる重量を12kg以下(男性の取り扱える重量の60%まで)
ということになります。
このことから、いかにボディメカニクスを活用しながらでも、移乗支援等が全介助となる要介護者を介護者一人で支援しようとすると、腰痛を来す危険性が高いということです。
そのため、介助での負担が大きい要介護者に関してはスライディングシートやトランスファーボード、介助用リフトなどの福祉用具・機器を活用しながら、『ノーリフティングケア』の観点での介助が必要となります。
まとめ
介護現場にて、職員の腰痛の発生率は高く、ボディメカニクスを活用した介護の実践など、腰痛対策は必要不可欠です。
職員全体でボディメカニクスを活用した介護を行っていくためには、組織全体での支援の方向性を定めることや、研修や指導などの教育体制なども必要となってきます。
腰痛予防の取り組みは、介護の質を向上させることや、介護職員の離職の防止に効果的です。
また、介護現場におけるボディメカニクスへの取り組みを継続していくことで介護の質向上、信頼・安心感といった地域での評判に繋がり、新規利用者の獲得など好循環へと繋がっていくことも期待できるでしょう。
ぜひ、今回の記事を参考にしていただきながら、ボディメカニクスを活用した介護の実践を進めていってください。
| この記事の執筆者 | こまさん 所有資格:作業療法士 経歴:作業療法士として医療分野では病院でのリハビリテーション業務に従事、介護分野では訪問リハビリテーション事業所を経て、現在は特別養護老人ホームの機能訓練指導員として従事。 入居者へ多職種で行う機能訓練の提供や、介護士への介護技術指導、LIFEや介護報酬改定に関わる業務などを担っている。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。