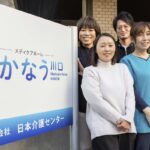ドラッグロックとは身体拘束のひとつで、薬物の過剰投与や不適切投与によってご利用者の行動を制限することです。
認知症ケアの現場では、徘徊や興奮状態への対応に苦慮することもあるでしょう。
その際、薬を用いるのではなく、行動の背景にある不快感や不安を丁寧にアセスメントし、多職種での連携を深め対策を行っていくことで、ドラッグロックのない質の高いケアの実現に向けた努力をする必要があります。
本記事では、ドラッグロックの定義や現場での具体例、対策方法などについて、厚生労働省などの資料をもとに詳しく解説します。
目次
ドラッグロックとは?

介護現場で避けるべき身体拘束の一つに「ドラッグロック」があります。
厚生労働省の「身体拘束廃止・防止の手引き」でも、薬物による抑制は身体拘束の一形態として問題視されており、適切なケアの重要性が強調されています。
ドラッグロックの概念も含めた身体拘束への理解を深めることで、ご利用者の尊厳や安全を守るケアに活かす第一歩となります。
身体拘束の定義と意味
介護現場における「身体拘束」とは、利用者の行動や意思表示を制限する目的で、身体の自由を奪う行為全般を指します。
厚生労働省の「身体拘束廃止・防止の手引き」では、介護保険指定基準において禁止されている行為を「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」と説明しており、「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」を除いて原則禁止されています。
たとえば、ベッドから転落しないように体をベルトで固定したり、車いすから立ち上がれないようにテーブルを固定したりする行為が該当します。
近年では、薬物による行動制限(ドラッグロック)も身体拘束の一形態として位置づけられています。
薬を使ってご利用者の徘徊や暴力行為などを抑える行為は、一見して拘束と分かりにくいですが、実質的に身体の自由や生活の質を奪う可能性があるため、厚生労働省は身体拘束の行為と位置づけています。
ドラッグロックが生じる背景と原因

ドラッグロックが生じる背景には、主に認知症ケアの難しさが大きく関わっているといえるでしょう。
認知症に伴うBPSD(行動・心理症状)は対応が複雑であり、徘徊や暴言、暴力行為などへの即効性のある対策として、薬物療法に頼りがちになる現実があります。
特に夜間の頻回な起き上がりや大声は、他のご利用者への影響も大きいといえます。
そうした場合、限られた人員で対応する介護現場では、薬物による行動コントロールが「解決策」として選ばれることがあります。
行動を抑制しないと本人、または他のご利用者に対してもケガの恐れが高まる、という背景がある場合もあるでしょう。
また、暴力行動に対して、職員の安全確保のため薬を使用している、といったケースも考えられます。
このように、様々な要因が複雑に関連してドラッグロックが発生しているともいえます。
ドラッグロックは「見えない拘束」とも呼ばれ、外見上は拘束しているようには見えないため気づきにくく、また治療目的の投与と混同されやすいという特徴もあります。
薬物による適切な治療と、不必要な行動制限を目的とした過剰投与は明確に区別する必要があるでしょう。
ドラッグロックとフィジカルロック・スピーチロックの違い
介護現場における身体拘束は「スリーロック」とも呼ばれ、フィジカルロック、ドラッグロック、スピーチロックの3種類に分類されます。
それぞれ異なる特徴を持ちますが、いずれもご利用者の行動を制限し、尊厳を損なう点では共通しています。
介護の質を高め、安全で安心なケアを提供するうえで、これらの違いを知っておくことは非常に重要です。
介護現場の3つのロックの定義と特徴
介護現場で問題視されている3つの「ロック」は、以下のように分類されます。
| 区分 | 定義・手段 | 具体例 |
| フィジカルロック | 身体的に拘束する行為 | ベッドに体を固定、ミトン手袋、立ち上がれない椅子の使用 |
| スピーチロック | 言葉によって行動を制限する行為 | 「動かないで」「勝手にトイレ行かないで」など |
| ドラッグロック | 薬剤を用いて行動を制限する行為 | 向精神薬や安定剤を過剰に使って落ち着かせる行為 |
いずれも身体機能や認知機能の低下を招き、ご利用者のQOL(生活の質)を低下させるリスクがあります。
厚生労働省は介護保険施設などにおいて身体拘束を原則禁止としており、これら3種類の拘束はいずれも「緊急やむを得ない場合」を除いて行ってはならない行為です。
介護現場における3つのロック、フィジカルロックやスピーチロックの詳細については以下の記事でまとめていますので、合わせて参考にしてください。
・身体抑制の三原則など、介護現場におけるスリーロック(3つの身体拘束)とは?
・フィジカルロックとは?具体例や事例、対策などを解説
・【言い換え表現例あり】スピーチロックとは?ご利用者への影響、防ぐポイントを解説
身体拘束のリスクと問題点

身体拘束は高齢者の心身に深刻な悪影響を与え、本来目指すべきケアの目標と正反対の結果をもたらします。
厚生労働省の「身体拘束廃止・防止の手引き」では、これらの弊害を3つの側面から整理しています。
身体的弊害
身体拘束はご利用者の身体機能を著しく低下させ、時には生命に関わる事故を引き起こす危険性があります。
・関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下
・圧迫部位のじょく創の発生
・食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下
・車いすからの転倒事故、ベッドからの転落事故の危険性増大
・抑制具による窒息等の重大事故のリスク
精神的弊害
身体拘束はご利用者本人だけでなく、ご家族や介護スタッフの精神的健康にも深刻な影響を与えます。
・ご利用者本人への不安、怒り、屈辱、あきらめなどの精神的苦痛
・人間としての尊厳の侵害
・認知症の進行、せん妄の頻発
・ご家族の混乱、後悔、罪悪感
・看護・介護スタッフの士気低下、ケアへの誇り喪失
社会的弊害と悪循環
身体拘束は個人の問題を超えて、介護制度全体への不信や経済的負担を生み出します。
・介護保険施設等への社会的不信、偏見の拡大
・心身機能低下による追加的な医療処置の必要性
・経済的負担の増大
・さらなる拘束が必要な悪循環の発生
・一時的拘束が常時拘束へと発展
この悪循環を断ち切ることで、高齢者の自立促進を図る「良い循環」への転換が可能になると手引きでは説明されています。
身体拘束をやむを得ず行う理由
介護現場では、身体拘束が「やむを得ない」とされる状況がいくつか挙げられます。
厚生労働省の「身体拘束廃止・防止の手引き」では、身体拘束をやむを得ず行う理由として、以下のような状況を防止するために「必要」と言われることがあると説明しています。
徘徊や興奮状態での周囲への迷惑行為
ご利用者が徘徊行動を取ったり、興奮状態になって他のご利用者や職員に影響を与える場合、これを制止するために身体拘束が検討されることがあります。
施設内での安全確保や他のご利用者への配慮から、こうした行動を物理的に制限しようとする判断がなされるケースです。
転倒のおそれのある不安定な歩行や点滴の抜去などの危険な行動
歩行が不安定で転倒の危険性が高いご利用者や、医療処置として行われている点滴などのチューブを自分で抜いてしまう恐れがある場合、安全確保を理由に身体拘束が行われることがあります。
特に医療的処置の継続が必要な状況では、治療効果を維持するための措置として検討されがちです。
かきむしりや体をたたき続けるなどの自傷行為
ご利用者が自分の体をかきむしったり、頭や体を叩き続けるなどの自傷行為を繰り返す場合、防止のために手の動きを制限する身体拘束が検討されることがあります。
皮膚の損傷や外傷を防ぐという観点から、やむを得ない措置として判断されるケースです。
姿勢が崩れ、体位保持が困難であること
身体機能の低下により、椅子や車椅子で適切な姿勢を保つことが困難なご利用者に対して、姿勢の維持や転落防止を目的として体幹を固定する拘束が行われる場合があります。
介護現場におけるドラッグロック対策
ドラッグロックを防ぐためには、組織全体で身体拘束廃止・防止に取り組み、利用者一人ひとりの状態を正確にアセスメントした上で、薬物に頼らないケアの実現を目指すことが重要です。
厚生労働省の「身体拘束廃止・防止の手引き」をもとに、以下の4つの視点から対策が求められます。
基本的な対策とアセスメント
・利用者の行動変化や生活背景を丁寧に記録し、薬物使用の必要性を多職種で検討。
・薬の効果・副作用の継続的観察を通じ、治療目的かどうかを見極める。
・「行動制限ではなく治療」の原則を常に意識。
ケアの質と環境整備
・「起きる・食べる・排せつ・清潔・活動」の5つの基本ケアを徹底。
・認知症の行動の背景にある要因を探り、個別ケアで対応。
・利用者の生活リズムや居室環境を整え、不安や混乱を軽減。
服薬管理と医療連携
・医師・薬剤師・看護師と連携し、薬剤の見直しを定期的に実施。
・ポリファーマシー(多剤併用)を避け、副作用リスクを最小限に。
・利用者ごとの服薬計画を作成し、職種間で情報共有。
研修・教育による意識向上
・経営層のリーダーシップのもと、全職員が共通認識を持つ。
・ドラッグロックの影響や対応策について実践的に学ぶ研修を継続。
・事例検討を通じ、成功事例・課題の共有と対応力向上を図る。
身体拘束の緊急やむを得ない場合の三原則(身体拘束の三原則)
身体拘束は原則として禁止されていますが、緊急時に限って「やむを得ない」と判断される場合のみ、例外的に認められます。
その際に必ず満たさなければならない条件が、「身体拘束の三原則」です。
三原則の内容と適用条件
厚生労働省が定める「身体拘束廃止・防止の手引き」では、以下の3つの条件をすべて満たす場合に限り、身体拘束が認められるとされています。
・切迫性
ご利用者本人または他のご利用者の生命や身体が危険にさらされるおそれが著しく高い状態であること(例:自傷行為、転倒による骨折リスクなど)
・非代替性
身体拘束以外に代わる手段がなく、他の方法では安全が確保できないこと(例:環境調整や見守り強化を行っても効果がない)
・一時性
身体拘束が必要な時間は最小限であり、拘束をやめる目処が立っていること(例:行動が落ち着いたら解除する、薬剤の影響が切れたら解除する)
この三原則は、1つでも欠ければ正当な身体拘束とは認められません。判断は現場の独断ではなく、多職種で検討し、記録・報告を必ず行う必要があります。
身体拘束の三原則については、以下の関連記事でも詳しく解説しています。
まとめ
ドラッグロックは、外見ではわかりにくいものの、ご利用者の自由や尊厳を大きく損なう可能性のある重大な問題です。
薬の使用そのものが悪いのではなく、その目的や使用状況によっては、身体拘束と同様にリスクの高い行為となることを、現場の介護職一人ひとりが理解しておく必要があります。
本記事では、ドラッグロックの定義や背景、判断基準、実際の事例、対策などについて公的資料をもとに解説しました。
ご利用者の安心と尊厳を守るためには、薬に頼らないケアの工夫、職員間の連携、そして一人ではなくチームで考える姿勢が何よりも大切です。
日々の業務の中で、少しずつでも改善を重ねながら、「その人らしい暮らし」を支える介護を実現していきましょう。
この記事の執筆者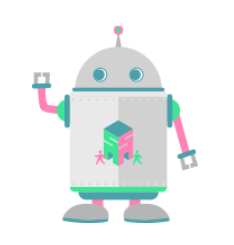 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。