介護現場において、コミュニケーションは介護サービスの質に関わる重要な項目です。
しかし、新人介護職の方や介護経験の浅い方の中には、「コミュニケーションの意味や目的を具体的に知りたい」という方もいると思います。
そこで今回は、介護におけるコミュニケーションの重要性についてお伝えします。利用者とのコミュニケーションを円滑に行うコツも紹介しますので、「高齢者とのコミュニケーションが苦手」という方も、ぜひご覧ください。
目次
介護におけるコミュニケーションの重要性
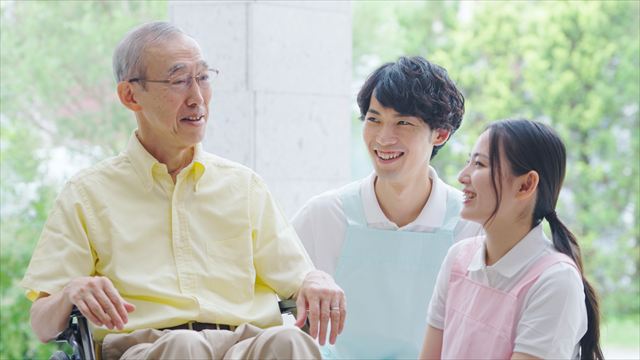
介護現場で行われるコミュニケーションの意味や目的、効果をみていきましょう。
利用者の状態を把握する
介護施設の利用者は、何らかの疾病や障がいを抱えています。
その日によって、心身の状態に変化があるかもしれません。
そのため、介護職員が「今日の調子はいかがですか?」「お変わりありませんか?」とコミュニケーションをとり、利用者の状態を把握する必要があるのです。
利用者の状態を把握することは、適切な介護サービスの提供に欠かせない業務です。
仮に利用者Aが「今日は膝が痛くていつも通り歩けないんだよね」と話したとしましょう。
その場合、利用者の状態を現場で共有することで、以下のような対応が可能になります。
・転倒や転落がないように注意する
・機能訓練士に運動メニューの相談をする
・痛みの経過を記録して、今後のサービスに役立てる
利用者の状態を把握するためには、相手とのコミュニケーションが欠かせません。
認知症の高齢者の中には、記憶や見当識(※)に障がいがある方もいます。体調を確認する際は、言葉の内容だけでなく、表情やジェスチャーにも注意してみましょう。
表情が暗かったりジェスチャーがなかったりと、明らかにいつもと違う様子があれば要注意です。記録を残したうえで、上司や先輩介護職に報告しましょう。
※今の時間や日付、今いる場所、自分と他人との関係性などの状況を認識すること
利用者の生活歴や価値観を知る
利用者の生活歴や価値観を深掘りして知りたいときに、コミュニケーションは役立ちます。
生活歴とは、その人の歩んできた生活の歴史です。氏名や住所が記載されたフェイスシートから、その概略を確認できるでしょう。
ただし、その人の生活を具体的に知るためには、コミュニケーションが重要です。
「転勤で北海道に来られたんですね。何年くらい北海道にいるのですか?」
「銀行で働かれていたんですね、印象に残っている出来事はありますか?」
といったような質問をすることで、文面からは確認できないリアルな情報にふれられるのです。
利用者を深く知ることは、お互いの距離を縮めることにつながります。
信頼関係をつくる
利用者に安心して介護サービスを受けてもらうためには、信頼関係が重要です。
もしも介護者が信頼されていなければ、利用者は介護に抵抗を示したり拒否したりするかもしれません。
利用者との信頼関係を築くためには、コミュニケーションを通じて介護者のことを知ってもらう必要があります。
コミュニケーションには、介助業務を円滑に提供するために必要な「相手との信頼関係をつくる役割」があるのです。
認知機能の維持や向上につなげる
高齢者の認知機能の維持・向上にも、コミュニケーションが大きな役割を果たします。
対面のコミュニケーションによって、高齢者の「社会的認知」が活発にできると考えられているからです。
社会的認知とは、人の気持ちに配慮したり、表情を適切に把握したりする能力を指します。
社会的認知は、認知症によって低下する脳の機能の1つです。
社会的認知の具体的な内容は以下のとおりです。
・相手の感情や意図をくみとる
・状況や文脈を理解する
・自分の発言を判断する
参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター|MCIハンドブック
介護職が積極的に利用者とコミュニケーションを図ることで、その人の認知機能の維持・向上に貢献できます。
介護サービスの質を向上させる
介護サービスの質を向上させるためには、利用者の意見や要望を聞くことが大切です。
介護サービスに対する率直な意見、「こうしてほしい」という要望を改善策に盛り込むことで、その人にあったサービスを実現できます。
その人にあった介護サービスの提供は、本人の自立支援や家族の満足度向上に結びつくでしょう。
介護サービスに対する率直な意見は、利用者とのコミュニケーションから確認するのが効果的です。
アンケート調査や聞き取り調査も有効ですが、利用者の本音がこぼれるのは、日常の些細なコミュニケーションの場面からです。
確認できた利用者の意見は、記録に残したり上司や先輩介護職に伝えたりして、介護サービスの質向上に役立てていきましょう。
介護現場のコミュニケーションを大切にしないリスク

介護現場のコミュニケーションを大切にしない場合、以下のようなリスクが生じます。
・利用者の体調不良を見過ごしてしまう
・支援に必要な情報を得られない
・ヒヤリハット、介護事故の発生
・介護サービスをスムーズに提供できない(介護されることへの抵抗、拒否)
・クレームが発生しやすくなる
コミュニケーションとは、言葉、声のトーン、表情、しぐさなどを通じて、お互いの考えや気持ちなどを伝えあう行為のことです。
コミュニケーションを軽視してしまうと、介護側が必要だと思う介護サービスを一方的に提供することになるかもしれません。
介護される側が安楽に介助してもらえるように、介護する側が気持ち良く介助するためにも、利用者とのコミュニケーションを大切にしていきましょう。
高齢者とのコミュニケーションが苦手な場合
高齢者とのコミュニケーションに苦手意識がある方は、以下のような悪循環に陥るおそれがあります。
苦手意識のせいでうまくコミュニケーションができない
↓
苦手意識が強くなる
↓
さらにコミュニケーションがうまくいかなくなる
↓
苦手意識が強くなる
悪循環に陥らないためには、まず「コミュニケーションがとりやすい」「話していて楽だ」と感じる人を頭に思い浮かべてみましょう。
次に、その高齢者とのコミュニケーションを多く持ってみます。
最後に、「ちょっと苦手だな」と感じる高齢者とコミュニケーションを図ってみてください。
徐々にハードルを上げていくことで、苦手意識を軽減しながらコミュニケーションを重ねていけます。
まずは「自分が楽にできること」から始めて、少しずつプレッシャーを感じることにトライしてみてくださいね。だんだんと自信が身についていくはずです。
介護現場のコミュニケーションを円滑に行うポイント
介護現場でのコミュニケーションを円滑に行うポイントを紹介します。
相手に興味を持ち質問する
「話題を提供しても、すぐ会話が終了してしまう」「良い質問が思い浮かばない」という場合は、相手に興味関心を持ってみましょう。
「相手のことをよく知りたい」と思うと、自然と聞きたいことが頭に浮かんでくるはずです。
また、相手に興味関心を持つとき、自分の声のトーンが高くなったり姿勢が前のめりになったりと、自分の態度に変化があらわれます。
そうした変化が相手に伝わり、自然と会話が弾むことがあるのです。
フェイスシートから相手の職歴や生活歴、家族構成などを確認して、興味を持てるポイントがないか探してみてください。
「話す」「聞く」の割合に気をつける
利用者との会話では、「話す」「聞く」の割合に気をつけてみましょう。
おすすめは、
「話す割合:聞く割合=3:7」
です。
話すより聞く方に重点を置くことで、「自分の話を聞いてくれる人」という印象を相手に与えられます。
「口数の少ない方が相手で、どうしても自分ばかり話してしまう」という際は、後述する質問の使い分けを活用してみてください。
なお、「話すよりも聞く方が好き」という利用者もいます。
自分から積極的に話すときは、相手に心配をかけたり気を遣わせたりするような話題(家族や親戚の不幸など)は避けてくださいね。
開かれた質問・閉ざされた質問
「自分ばかり話してしまう」「質問の仕方がわからない」といったケースでは、「開かれた質問」「閉ざされた質問」を使用してみましょう。
| 開かれた質問 | 閉ざされた質問 | |
| 特徴 | 一言で答えにくい質問 | 「はい」「いいえ」「良い」「悪い」のように、一言で答えられる質問 |
| 具体例 | 「今日の調子はいかがですか?」 「お休みの日はどのように過ごされていましたか?」 |
「今日の体調は良いですか?」 「お休みの日は家で過ごしていましたか?」 |
| 活用方法 | ・利用者の考えや気持ちを引き出したいとき ・会話を広げたいとき |
・自由に話すのが苦手な人と会話するとき ・口数が少ない人との会話に ・認知症の高齢者との会話にも効果的 |
質問の種類を使い分けられるようになると、相手に合わせた接し方ができるようになります。また、会話の中にリズムが生まれる点もポイントです。
非言語コミュニケーションを活用する
非言語コミュニケーションとは、言葉に頼らない意思疎通の手段です。
ノンバーバル・コミュニケーションとも呼ばれます。
非言語コミュニケーションでは、表情、声のトーン、相づち、手振りなどを活用し、言葉以外の手段によって利用者とコミュニケーションを図ります。
非言語コミュニケーションの良いところは、言葉以外の手段によって傾聴の姿勢を示せる点です。
相手の話に相づちをうったり、深く頷いたり、柔らかい表情をつくったりすることで、「私はあなたを受け入れます」という姿勢を相手に示せます。
非言語コミュニケーションは、認知症の高齢者のように見当識障がいや言語障がいのある方に対しても有効なコミュニケーションです。
沈黙をコミュニケーションにいかす
会話の中でふと訪れる「沈黙」には、2つの意味・目的があります。
1つは、ここまでのコミュニケーションの内容を整理する時間です。
沈黙によって、話の内容を整理したり利用者の状況などを受けとめたりする時間をつくれます。
こうした作業を通じて、相手をありのままに受け入れるための準備ができるでしょう。
沈黙のもう1つの意味は、相手の話を待つことです。
「あなたの言葉を待っていますよ」という姿勢を相手に示すことで、利用者は自分が大切に扱われていると感じてくれます。
「ゆっくり話していいですよ」と伝えてから、再度待つとより丁寧な印象を与えられるでしょう。
共感の姿勢を持つ
利用者の話を聞いて「自分だったら、同じ状況でどのように感じだろうか」「何を思うだろうか」と想像することは、共感と呼ばれるコミュニケーション技法です。
共感する姿勢を持つと、自分の態度や言葉が、自然と相手の気持ちに寄り添ったものになります。
その結果、「この介護職員は、私のことを考えてくれている」と利用者に感じてもらいやすくなるのです。
共感の姿勢は、互いの心が通いあうようなコミュニケーションの実現にも役立ちます。
会話のネタをストックしておく
会話のネタをストックしておく方法も効果的です。
ネタを用意すると、会話が途切れたときや場を盛り上げたいときに活用できます。
どの介護現場にも共通して使える会話のネタは次のとおりです。
・新聞やテレビで話題になっているもの
・利用者が興味のあるジャンル
・利用者の趣味と関連の深いニュース
・介護施設のある地域、利用者の暮らしている住所と関係のある話題
会話のネタは、出勤前日の夜や当日の朝に仕入れておくのがおすすめです。
介護現場で避けるべきコミュニケーション

介護現場では、避けるべきコミュニケーションがあります。
その種類と具体例を下表にまとめました。
| 避けるべきコミュニケーション | 具体例 |
| スピーチロック | 動かないで、話さないで、待ってて |
| 尊厳を傷つける話し方 | こんなこともできないの? |
| 幼児言葉の使用 | おねんねしましょうね |
| 他人の悪口・陰口 | 他の利用者や職員が傷つくような話題 |
| 威圧的な態度 | 怒鳴る、必要以上に近づく、睨むなど |
このような言動は、利用者との関係性悪化や介護施設への不信感につながるため、日頃から口にしないように注意する必要があります。
スピーチロックの防ぎ方や言い換え例を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【言い換え表現例あり】スピーチロックとは?利用者への影響、防ぐポイントを解説
介護職に求められる言葉遣いや接遇マナーを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
介護職に求められる言葉遣いとは?【チェックリスト付き】接遇マナーも解説
介護現場では一人ひとりに合わせたコミュニケーションが重要
利用者や家族の満足度を高めるためには、相手に合わせたコミュニケーションが重要です。
たとえば、難聴のある利用者に対して、筆談を用いたり聞こえやすい声のトーンを心がけたりする方法は、介護職ならではの工夫です。
一方で、「Aさんは認知症だから~ができない」「Bさんは要介護1だから~ができない」と、疾病や要介護度をもとに利用者を決めつけることはおすすめできません。
「相手の方ができること、やりたいことは何か」と考えることが、利用者が喜ぶようなコミュニケーションに結びつくはずです。
一人ひとりの個性や特徴に合わせたコミュニケーションを心がけましょう。
まとめ
介護におけるコミュニケーションの重要性についてお伝えしてきました。
介護現場におけるコミュニケーションの意味や目的を下記にまとめます。
・利用者の状態を把握する
・生活歴や価値観を知る
・信頼関係をつくる
・認知機能の維持・向上
・介護サービスの質向上
利用者の気持ちに寄り添った介護サービスを提供したいときは、コミュニケーションに力を入れてみましょう。
また、「利用者とのコミュニケーションが苦手」「コミュニケーションが上手な同僚と自分を比べて落ち込んでしまう…」という方も焦る必要はありません。
コミュニケーション技術は、日々の業務経験を積む中で徐々に磨かれていきます。
コミュニケーションの基本から一つずつ身につけていきましょう。
| この記事の執筆者 | 千葉拓未 所有資格:社会福祉士・介護福祉士・初任者研修(ホームヘルパー2級) 専門学校卒業後、「社会福祉士」資格を取得。 以後、高齢者デイサービスや特別養護老人ホームなどの介護施設を渡り歩き、約13年間介護畑に従事する。 生活相談員として5年間の勤務実績あり。 利用者とご家族の両方の課題解決に尽力。 現在は、介護現場で培った経験と知識を生かし、 Webライターとして活躍している。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。





















