グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を運営する上で、人員基準を正しく理解し、適切な職員配置を行うことは非常に重要です。
人員基準を満たせない場合、介護報酬の減算や行政処分を受けるリスクがあり、事業所の経営に深刻な影響を及ぼしてしまいます。
この記事では、グループホームの人員基準や計算方法について、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者といった職種ごとの配置基準と、常勤換算による具体的な計算方法を分かりやすく解説します。
また、2021年介護報酬改定による変更点や、常勤換算する際の注意点、人員基準違反時のリスクについても詳しくご紹介します。
グループホームの人員基準

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症の方が少人数で共同生活を送る小規模な介護施設で、1ユニット5~9人の少人数体制で、家庭的な環境の中でケアを提供することが特徴です。
厚生労働省が定める人員基準に基づき、適切な職員配置を行うことが義務付けられています。
定められた人員基準は、ご利用者に質の高い介護を提供し、安全を守るための重要な基準です。
グループホームで配置が必要な職種は、介護職員、計画作成担当者、管理者、代表者です。
人員基準の対象となる4つの職種
グループホームでは、厚生労働省により4つの職種について人員配置が義務付けられています。
それぞれの職種には異なる配置基準や資格要件が定められており、これらを正しく理解することが適切な施設運営の基礎となります。
ここでは各職種の役割と基本的な配置基準について簡潔に紹介します。
介護職員
介護職員は、ご利用者の日常生活の介助やレクリエーション活動などを担当する職種です。
食事、入浴、排泄といった身体介護から、家事援助、見守りまで、ご利用者の生活を24時間体制でサポートします。
介護職員の人員基準は、日中はご利用者3人に対して1人以上、夜間はユニットごとに1人以上の配置が必要と定められています。
この基準は常勤換算で計算されるため、常勤職員と非常勤職員を組み合わせた配置が可能です。常勤換算の計算方法については後述します。
計画作成担当者
計画作成担当者は、ご利用者一人ひとりの介護計画(ケアプラン)を作成する職種です。
ご利用者の心身の状態やニーズを把握し、適切な支援内容を計画する重要な役割を担います。
ユニットごとに1人の配置が必要で、ユニット間の兼務はできません。
計画作成担当者のうち最低1人は介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格が必要です。
また、すべての計画作成担当者は認知症介護実践者研修を修了している必要があります。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護」
管理者
管理者は、事業所全体の運営管理を担当する職種です。
職員の勤務管理、ご利用者の受け入れ調整、施設全体の統括など、幅広い業務を担います。
ユニットごとに常勤専従で1人の配置が必要です。
管理者になるには、3年以上の認知症介護従事経験があり、認知症介護実践者研修および認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していることが必須となります。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護」
代表者
代表者は、事業所の開設者にあたる立場で、理事長や代表取締役などが該当します。
認知症対応型サービス事業開設者研修の修了が必須となります。
新規事業を開始する場合は、事前に研修を修了している必要があります。
ただし、代表者が交代する場合は、半年以内または次回研修日のいずれか早い日までに修了すればよいとされています。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護」資料19ページ、26ページ
各職種の詳細な人員基準や資格要件、必要な研修などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
グループホームの人員基準と計算方法

グループホームの人員基準と計算方法についてです。「常勤換算」を用いて必要な職員数を計算します。
常勤換算とは、常勤職員と非常勤職員の勤務時間を合算し、常勤職員の人数に換算する計算方法です。
特にグループホームにおける介護職員については、日中と夜間で配置基準が異なるため、それぞれ適切に計算する必要があります。
ここでは、常勤換算の基本的な考え方と、具体的な計算例を用いて分かりやすく解説します。
常勤換算の詳しい仕組みについては、以下の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。
日中の人員基準(利用者3人に対して1人以上)
日中の配置基準の詳細
日中の時間帯における介護職員の配置基準は、ご利用者3人(またはその端数)に対して常勤換算で1人以上と定められています。
重要なポイントは、日中の介護職員の勤務時間合計が24時間以上必要であることと、常に1人以上の介護職員が配置されていることが求められる点です。
これらは厚生労働省の指定基準で明確に定められていて、例えば、ご利用者が9人の場合、9人÷3人=3人となり、常勤換算で3人以上の介護職員を配置する必要があります。
参照:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護」
常勤換算の計算
常勤換算の計算式は以下のとおりです。
常勤換算人数 = 常勤職員数 + (非常勤職員の勤務延時間数 ÷ 常勤職員の勤務すべき時間数)
常勤職員の勤務すべき時間数は、事業所ごとに定められた時間となります。
一般的には週40時間(1日8時間×週5日)が基準となることが多いです。
例えば、常勤職員が週40時間勤務する事業所で、非常勤職員が週20時間勤務する場合、非常勤職員1人は常勤換算で0.5人となります。
計算結果に端数が生じた場合、小数点第2位を四捨五入するのが一般的です。
この計算方法を用いることで、多様な勤務形態の職員を組み合わせながら、人員基準を満たす配置が可能になります。
夜間の人員基準(ユニットごとに1人以上)
夜間の配置基準の詳細
夜間および深夜の時間帯においては、各ユニットに1人以上の夜勤職員を配置する必要があります。
夜間の時間帯とは、一般的に夕方から翌朝までの時間帯を指しますが、具体的な時間設定は事業所ごとに定めることができます。
夜勤職員は、夜勤または宿直勤務として配置され、ご利用者の安全確保や緊急時の対応を行います。
1ユニットの場合は1人、2ユニットの場合は2人の夜勤職員が必要となるのが基本です。
夜間は日中に比べて職員数が少なくなるため、見守りシステムなどのICT機器を活用する事業所も増えています。
2021年改定による夜間配置基準の緩和

2021年の介護報酬改定により、3ユニットの場合の夜間配置基準が一部緩和されました。
従来は3ユニットの場合、夜勤職員を3人配置することが必須でしたが、改定後は一定の要件を満たせば2人以上の配置を選択することが可能になりました。
この緩和が適用される要件は以下のとおりです。
・各ユニットが同一階に隣接していること
・職員が円滑にご利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造であること
・安全対策が実施されていること(マニュアルの策定、訓練の実施)
この緩和措置は事業所の選択制であり、従来どおり3人配置を継続することも可能です。
2人配置を選択する場合は、別途の報酬が設定されています。
緩和要件を満たさない場合や、より手厚い体制を希望する場合は、引き続きユニットごとに1人ずつの配置が必要です。
参照:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」P41
介護職員の人員基準計算の具体例
計算例1:1ユニット(利用者9人)の場合
1ユニット、ご利用者9人のグループホームにおける人員基準の計算例を示します。
【前提条件】
・ご利用者数:9人
・常勤職員の勤務時間:週40時間(1日8時間×週5日)
【日中の必要人数の計算】
9人÷3人=3人
常勤換算で3人以上の介護職員配置が必要です。
また、日中の介護職員の勤務時間合計が24時間以上必要で、常に1人以上の介護職員が配置されていることが求められます。
【夜間の必要人数】
1ユニットにつき夜勤職員1人の配置が必要です。
計算例2:2ユニット(利用者18人)の場合
2ユニット、ご利用者18人のグループホームにおける人員基準の計算例を示します。
【前提条件】
・ご利用者数:18人(各ユニット9人)
・常勤職員の勤務時間:週40時間(1日8時間×週5日)
【日中の必要人数の計算】
18人÷3人=6人
常勤換算で6人以上の介護職員配置が必要です。
1ユニットの場合と同様に、日中の介護職員の勤務時間合計が24時間以上必要で、常に1人以上の介護職員が配置されていることが求められます。
【夜間の必要人数】
2ユニットで夜勤職員2人(各ユニット1人ずつ)の配置が必要です。
常勤換算する際の注意点

常勤換算を用いて人員基準を計算する際には、いくつかの重要な注意点があります。
有給休暇、出張、兼務、産休・育児休暇などの扱いを正しく理解していないと、誤った計算につながり、結果的に人員基準欠如となる可能性があります。
特に管理者や勤務管理を担当する方は、これらのルールを正確に把握しておくことが大切です。
ここでは、特に注意が必要な3つのポイントについて詳しく解説します。
有給休暇・出張の扱い
有給休暇を取得した日は、実際には勤務していませんが、常勤換算の計算では勤務時間に含めることができます。
これは労働基準法で保障された権利である有給休暇の取得を妨げないための配慮です。
同様に、出張で事業所を離れている時間も勤務時間として計算可能です。
事業所の業務として参加する研修や会議についても、勤務時間に算入することができます。
ただし、職員が自主的に参加する事業所外での研修や勉強会については、業務命令によるものでない限り勤務時間には含められません。
これらの取扱いは厚生労働省の通知に基づいており、適切に運用することで職員の権利を守りながら人員基準を維持できます。
兼務の扱い
同一事業所内において、複数の職種を兼務することは原則として認められています。
例えば、管理者がご利用者の処遇に支障がない範囲で介護職員を兼務することは可能です。
計画作成担当者も、管理者との兼務が認められています。
ただし、同時に複数の職務を行うことはできないため、兼務する場合は各職種の勤務時間を明確に区分する必要があります。
具体的には、勤務シフト表などで「この時間帯は管理者業務」「この時間帯は介護職員業務」といった形で記録を残すことが重要です。
兼務時間は按分して計算し、それぞれの職種の常勤換算に反映させます。
適切な記録管理により、実地指導の際にも兼務の妥当性を説明できるようにしておきましょう。
産休・育児休暇の扱い
産前産後休業、育児休業、介護休業を取得している職員は、原則として常勤換算の計算には含まれません。
ただし、令和3年度介護報酬改定により、「常勤」での配置が求められる職員が産休・育休等を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことが認められています。
また、育児・介護休業法による短時間勤務制度を利用する場合は、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことができます。
参照:厚生労働省「人員配置基準等(介護人材の確保と介護現場の生産性の向上)」令和5年9月 P6
グループホームの人員基準を満たせない場合のリスク
人員基準を満たせない状態が生じた場合、事業所は深刻なリスクに直面します。
主なリスクは「人員基準欠如減算」と「行政処分」の2つです。
人員基準欠如減算は介護報酬が大幅に減額されるため、事業所の収入に直接的な影響を及ぼします。
さらに、虚偽の報告を行った場合には、事業所指定の取り消しといった重い行政処分を受ける可能性もあります。
ここでは、それぞれのリスクの内容と、どのような影響があるのかを詳しく解説します。
人員基準欠如減算
人員基準欠如減算とは、人員配置基準を下回った場合に適用される介護報酬の減算です。
減算の内容は、人員基準上必要とされる員数からの減少割合によって異なります。
人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合は、翌々月から人員基準欠如が解消されるまで基本報酬の30%が減算されます(所定単位数×70/100)。
人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は、翌月から人員基準欠如が解消されるまで基本報酬の30%が減算されます(所定単位数×70/100)。
この減算は、ご利用者全員に対して適用されるため、事業所の収入は大幅に減少します。
例えば、月の介護報酬が300万円の事業所で人員基準欠如減算が適用された場合、90万円(300万円×30%)が減額され、収入は210万円となります。
この状態が続けば、人件費や運営費の支払いが困難となり、事業継続に支障をきたす可能性があります。
人員基準欠如減算についての詳細は、以下の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。
行政処分のリスク
人員基準違反を行い、さらに虚偽の報告を行った場合は、行政処分の対象となります。
人員基準違反が発覚した場合、まず運営指導(実地指導)が行われ、違反が確認されると監査に移行します。監査の結果、違反の程度や悪質性によって、以下のような段階的な行政処分が決定されます。
1.行政指導による改善報告:違反事実を指摘し、改善を求める
2.改善勧告:改善指導に従わない場合、勧告を行う
3.改善命令(公示):改善勧告に従わない場合、法的拘束力のある命令を出す
4.指定の効力の停止(一部・全部):一定期間、新規利用者の受け入れ停止や事業の全部または一部が停止される
5.指定の取り消し:事業所としての指定が取り消され、介護事業を行えなくなる
令和5年度の厚生労働省の調査によると、指定取消・効力停止処分は139件に達しています。処分の内訳は、指定取り消し60件、指定の効力の一部停止64件、全部停止15件となっています。
処分の主な理由としては、不正請求(69件、49.6%)が最も多く、次いで人員基準違反(45件、32.4%)、虚偽報告(34件、24.5%)、虚偽答弁(29件、20.9%)、人格尊重義務違反(29件、20.9%)などが挙げられています。
参照:厚生労働省「介護サービス事業所等に対する指導・監査結果の状況」(令和5年度)
なお、1つの事業所に対して複数の処分事由が該当する場合があるため、処分事由の合計は139件を上回ります。
特に認知症対応型共同生活介護(グループホーム)においては、令和5年度に21件の指定取り消し・効力停止処分が発生しており、訪問介護と並んで最も処分件数の多いサービス種別となっています。
事業所指定が取り消された場合、ご利用者は他の施設への移転を余儀なくされ、職員も職を失うことになります。
このような事態を避けるためにも、日頃から適切な人員配置と正確な記録管理を行うことが極めて重要です。
グループホームの人員基準違反による行政処分の詳細や、違反を防ぐための具体的な対策については、以下の記事で詳しく解説しています。また、実地指導についての記事も掲載していますので、合わせて参考にしてください。
まとめ
グループホームの人員基準や計算方法について解説しました。
グループホームの人員基準は職種ごとに明確に定められていますので、これを遵守することが適切な施設運営の基本となります。
介護職員については、日中はご利用者3人に対して常勤換算で1人以上、夜間はユニットごとに1人以上の配置が必要です。
また、2021年の介護報酬改定では、3ユニットの場合の夜間配置基準が一部緩和され、要件を満たせば2人以上の配置を選択できるようになりました。しかし、安全性なども考慮して適切な人員配置を考えることが大切だといえるでしょう。
グループホームにおいて適切な人員配置を行うことは、ご利用者に質の高いケアを提供すると同時に、職員の負担を軽減することにもつながります。安定した事業所運営の実現につなげていきましょう。
グループホームの適切な人員配置に役立つ介護業界向けシフト管理システムについてはこちらをご覧ください。
この記事の執筆者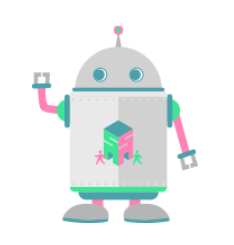 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。






















