介護現場では、利用者の安全を守ることは最優先の課題です。
しかし、どれほど注意深く業務を行っても、転倒や誤薬などの事故が発生してしまうことがあります。
介護事故を完全にゼロにすることは現実的には非常に困難ですが、適切な知識と対策により、防ぐことができる事故は確実に減らすことができます。
介護事故防止には組織全体で対応することが欠かせません。
リスクマネジメントの手法、ヒヤリハット事例の活用、ICTツールの導入、最適な人員配置も重要なポイントとしてあげられるでしょう。
本記事では、介護事故の定義や種類、具体的な事例から、効果的な防止策まで解説します。
目次
介護事故の定義とは
厚生労働省が公表している介護事故の定義は以下の通りです。
『社会福祉施設における福祉サービスの全過程において発生する全ての人身事故で身体的被害及び精神的被害が生じたもの。なお、事業者の過誤、過失の有無を問わない。』
引用:厚生労働省 「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針 ~利用者の笑顔と満足を求めて~」について
この定義で重要なポイントは、職員の過失があったかどうかに関わらず、利用者に実害が生じた場合は介護事故として扱われることです。
例えば、適切な介助を行っていても、利用者の予期せぬ動きによって転倒や所有物の破損・紛失などが発生した場合も事故に含まれます。
そのため、介護現場においては起こりうる事故を予測し、事故が発生しないように対策を取ることが重要です。
軽微な事故やヒヤリハット事例も含めて、予防対策を重ねていくことが大切だといえるでしょう。
介護事故の種類と事例

介護現場で発生する事故にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特徴や発生要因を持っています。
介護労働安定センターが実施した調査を参考に、代表的な事故の種類とその特徴について、統計データとともに具体的な事例をみていきましょう。
介護労働安定センターの平成30年度調査では、276事例の事故状況を分析した結果、
・転倒・転落・滑落: 181件(65.6%)
・誤嚥・誤飲・むせこみ: 36件(13.0%)
・不明: 33件(12.0%)
・その他: 16件(5.8%)
・送迎中の交通事故(接触・追突): 7件(2.5%)
・ドアに体を挟まれた: 2件(0.7%)
・盗食・異食: 1件(0.4%)
という結果が報告されています。
参照:公益財団法人 介護労働安定センター「介護サービスの利用に係る 事故の防止に関する調査研究事業」 報告書 P.3
これらのデータから分かるように、「転倒・転落・滑落」事故が全体の約3分の2を占めており、介護現場で最も注意すべき事故類型となっています。
また、「誤嚥・誤飲・むせこみ」が13%と2番目に多くなっています。
これらの主要な事故パターンを理解し、施設の環境整備、業務にあたる介護職の知識・スキル面も含めて、適切な対策を講じることが事故防止に重要です。
転倒
転倒事故は介護現場で最も発生頻度の高い事故です。
高齢者は筋力低下やバランス機能の衰え、認知機能の低下などにより、転倒リスクが高くなっています。
転倒事故が発生しやすい場面としては、移動時や立ち座りの動作時、方向転換時、急な動作を行った時などがあげられます。
また事故の発生につながる環境要因としては、床の濡れや段差、照明不足、履物の不適合といったことがあります。
転倒事故の事例
・夜間トイレ移動時にカーペットの端につまずいて転倒
・食堂での立ち上がり時にバランスを崩して転倒
・入浴介助中に濡れた床で滑って転倒
・居室内でスリッパを履いたまま歩行中に転倒
・廊下歩行中に他の利用者とぶつかりそうになって避けようとして転倒
これらの事例は、利用者の身体機能の低下、環境要因、時間帯による身体状況の変化など複合的に関連して発生することが考えられます。
日常的な動作の中で起こる可能性もあるため、介護職員による適切な見守り、事故の要因リスクを無くすための環境整備が重要です。
転落
転落事故は転倒に次いで発生頻度の高い事故で、主にベッドや車椅子、椅子などからの落下によって発生します。
高所からの落下により重篤な外傷を負うリスクがあります。
転落事故が発生しやすい場面として、ベッドからの起き上がりや移乗時、車椅子からの立ち上がり時、入浴時の浴槽への移乗時などが挙げられます。
転落事故の事例
・ベッドサイドレールを乗り越えようとして転落
・ポータブルトイレ使用中に体勢を崩して転落
・入浴時のシャワーチェアからバランスを崩して転落
・浴介助中に浴槽の縁に足を滑らせ転落
・ベッドから車椅子への移乗時にバランスを崩して転落
誤嚥
誤嚥事故は、食べ物や飲み物が誤って気管に入ってしまう事故で、重篤な結果を招く可能性が高い危険な事故類型です。
介護労働安定センターの調査では、全事故の13%を占めており、死亡事故につながるケースも多く報告されています。
高齢者は嚥下機能の低下により誤嚥リスクが高く、特に認知症の利用者や脳血管疾患の既往がある利用者では注意が必要です。
誤嚥事故は食事時だけでなく、水分摂取時や服薬時にも発生する可能性があります。
誤嚥事故の事例
・食事中に固形物を噛み砕かずに飲み込んでしまった
・服薬時の水の量が少なく錠剤が気管に入ってしまった
・夜間就寝中の唾液誤嚥
・嚥下機能が落ちている利用者に、謝って通常食を提供してしまった
誤薬
誤薬事故は、本来投与すべき薬とは異なる薬剤の投与や、投与時間・投与量の間違いによって発生する事故です。
誤薬事故の主な原因として、薬剤管理の不備、確認作業の不足、情報共有の欠如、職員の思い込みなどが挙げられます。
特に複数の利用者の薬剤を同時に管理する施設では、誤薬を防ぐために、薬のダブルチェック体制の確立、薬品棚の整理、電子カルテの活用など、十分な注意と確認体制が必要です。
誤薬事故の事例
・同じテーブルの他の利用者の降圧薬を誤って服用し血圧低下
・朝の薬と昼の薬を取り違えて配薬
・薬包の名前確認不足により別人の薬を投与
・認知症の利用者が他人の薬を勝手に服用
・薬剤師からの変更連絡が職員に伝わらず旧薬を継続投与
介護事故の原因

介護事故が発生する原因は、職員側の要因、利用者側の要因、環境的な要因などが複雑に絡み合っていることが多いといえます。
介護事故防止のためには、これらの要因を正しく理解し、それぞれに対する適切な対策を組織全体で考えて実施していくことが重要です。
ここでは、介護現場で事故が発生する主な原因について、具体的に解説します。
職員側の要因
人手不足の介護施設も多いのが現状でしょう。
介護の現場は多忙なうえ、人手不足から慢性的に業務過多の状況になっていると、職員の疲労やストレスからくる注意力の散漫・ミス、人員的に見守りが手薄になるなど、事故がより起こりやすくなってしまいます。
介助技術の不足も事故の要因となります。
特に新人職員や経験の浅い職員は、利用者の状態変化を見逃したり、適切な介助方法を選択できないリスクがあります。
また、多忙な業務による確認作業の省略や焦りによるミスも、事故につながる重要な要因です。
職員間の情報共有不足により、利用者の状態変化に気づかずに事故につながるケースも少なくありません。
利用者側の要因
利用者自身の加齢に伴う身体機能の低下、筋力やバランス能力の衰え、視力や聴力の低下が事故リスクを高めます。
認知症の進行により危険認識能力が低下し、予測困難な行動を取ることで事故につながる場合もあります。
また、薬剤の副作用によるふらつきや眠気なども、転倒事故の要因となることがあります。
これらは完全に予防することは困難ですが、適切なアセスメントと個別対応により、リスクを最小限に抑えることは可能です。
環境的な要因
施設の環境や設備も介護事故の要因となり得ます。
床の段差や滑りやすさ、照明不足、手すりの設置不備、福祉用具の不適切な使用や故障などが事故の原因となります。
また、環境的な要因として、利用者の身体状況に合わない車椅子やベッドの使用、薬剤の保管方法の不備なども含まれます。
こうした要因に関しても、事故予防のために定期的に見直すことが大切だといえるでしょう。
「防ぐべき介護事故を防止」することが重要

介護現場における事故防止を考える上で、すべての事故をゼロにすることは現実的ではありません。
利用者の心身の状態は常に変化し、予測不能な行動や突発的な状況が発生する可能性があるためです。
介護現場において重要なのは「防ぐことができる事故を確実に防止する」という考え方です。 この章では、現実的な事故防止の取り組み方について解説します。
介護現場で事故をゼロにすることは非常に難しい
介護サービス利用者は、身体機能や認知機能が低下している方、認知症の方などもいるため、健康な方と比較して事故リスクが高い状態にあります。
現場においては限られた人員で基準ギリギリで多くの利用者をケアしているのが現状です。
そのため介護事故防止のために常にマンツーマンで利用者を見守り続けることは非常に困難です。
また、利用者の生活の質を尊重することも重要です。過剰な安全対策は利用者の自由を奪い、QOL(生活の質)を低下させることにもなりかねません。
例えば、転倒を恐れて活動を制限しすぎると、利用者の身体機能や意欲の低下を招いてしまう恐れがあります。
このような現実を踏まえると、介護現場において事故発生率をゼロにすることは極めて困難です。
しかし、だからといって事故防止の努力を怠っても良いということではありません。
適切なアセスメントと予防策の実施により、多くの事故は防ぐことが可能です。
そのため、事故防止の取り組みでは、「完全に防げる事故」と「防ぐことが困難な事故」を区別して考えることが重要といえるでしょう。
例えば、確認不足による誤薬事故や、不適切な環境設定による転倒事故などは、適切な対策により防ぐことが可能です。
一方で、予期せぬ利用者の行動や、既存の疾患による突発的な症状などは、完全に防ぐことが困難な場合があります。
職員数が限られる中、介護現場では防ぐべき事故の優先順位を明確にし、組織全体で計画的な事故防止対策に取り組むことがとても重要だといえるでしょう。
介護事故を防ぐためのリスクマネジメント
リスクマネジメントとは、介護現場で発生する可能性のあるリスクを事前に特定し、分析・評価した上で適切な対策を講じる予防的な取り組みです。
リスクマネジメントの基本的な流れは、
「リスクの特定」→「リスクの分析」→「リスクの評価」→「リスクへの対応」
という4つのステップで構成されます。
リスクマネジメントの具体的な手法や導入については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
介護事故防止のためのヒヤリハット事例と活用法

ヒヤリハット事例の収集と活用は、介護事故を未然に防ぐための最も効果的な手法の一つです。
この章では、ヒヤリハットの重要性と具体的な活用方法について解説します。
ヒヤリハットの定義と重要性
ヒヤリハットとは、介護事故には至らなかったものの、「ヒヤリ」「ハッ」とするなど、もう少しで事故になりそうだった状況のことを指します。
実際の事故は発生していないものの、一歩間違えれば重大な事故につながる予兆として、事象を記録・分析することで、事故の予兆を早期に発見できます。
ハインリッヒの法則が示すように、1つの重大事故の背景には29件の軽微な事故があり、さらにその背景には300件のヒヤリハットが存在します。
この法則から分かるように、ヒヤリハット段階で適切な対策を講じることで、将来発生する可能性のある重大事故を予防できるということになります。
ヒヤリハット報告を効果的に活用するためには、職員が報告しやすい環境づくりが重要です。
そのために重要なのは、ヒヤリハット報告を個人の責任追及ではなく、組織の改善につなげる情報収集として位置づけることです。
報告に対して、「貴重な情報をありがとう」という姿勢で受け止めることで、職員が安心して報告できる環境を作ることが大切です。それにより、組織全体の安全レベル向上につなげることができます。
報告されたヒヤリハット事例を職員間で共有し、類似した状況での注意喚起や予防策の検討に活用していきましょう。
具体的なヒヤリハット事例
ヒヤリハット事例を紹介します。
・夜間のトイレ介助時、利用者がベッドから降りる際にふらつき、職員が支えて転倒を回避した
・配薬時に隣の利用者の薬を取りそうになったが、薬袋の名前を確認して誤薬を防いだ
・入浴介助中にシャワー温度が高くなりかけたが、すぐに気づいて調整し事なきを得た
・ベッドから車椅子への移乗時、利用者が立ち上がるタイミングがずれたものの、職員が支えて事故を防ぐことができた
これらのヒヤリハット事例を記録し、「なぜそのような状況が発生したのか」「どのような対策が有効か」を職員全員で検討、対策を実施することで、同様の事故の発生を防ぐことができるでしょう。
時間帯や場所、関わった職員の経験年数などの情報も併せて記録することで、事故発生のパターンを把握し、より効果的な予防策を立案できます。
介護現場で実際に発生したヒヤリハット事例と対策については、以下の関連記事で詳しく紹介しています。合わせてご覧ください。
介護事故が起きてしまった場合の対応

どんなに注意深く事故防止策を講じても、介護現場では事故が発生してしまうことがあります。
ここでは介護事故が起きた後の対応の流れについて解説します。
利用者の安全を確保する
事故発生時の最優先事項は、利用者の安全確保です。意識状態、呼吸状態、外傷の有無を迅速に確認し、必要に応じて応急処置を行います。
また、重篤な状態が疑われる場合は直ちに救急搬送の手配を行います。
応急処置では、二次的な事故を防ぐため無理な移動は避け、医療従事者の指示を仰ぎます。
ご家族・関係者への報告、謝罪
事故が発生した場合、速やかにご家族へ連絡を行うことも大切です。
・事故の内容
・利用者の状態
・今後の対応について
事故に対する謝罪の気持ちを伝え、事実に基づいた正確な情報のみを説明し、事実関係が不明確な部分は調査中である旨を伝えます。
担当ケアマネジャーや主治医などにも速やかに事故状況を報告し、今後のケアについて連携を図るようにしましょう。
介護事故の内容に応じ関連機関へ報告
介護事故の内容によっては、市町村や都道府県への報告が義務付けられています。
死亡事故や重篤な事故、骨折などの重大な怪我、食中毒や感染症の発生などが報告対象となります。
事前に所在地の自治体の報告基準と手続きを確認し、緊急時に迅速に対応できるよう準備しておくことが重要です。
事故の記録
事故発生時の状況を正確に記録することは、原因分析や再発防止において重要です。
記録すべき主な内容は以下の通りです。
・事故発生の日時、場所
・関係者の氏名と役割
・事故の具体的な状況
・利用者の状態(意識、外傷の部位と程度など)
・実施した応急処置の内容と時刻
・医療機関への連絡
・受診の有無と結果
・ご家族や関係機関への連絡状況
フォーマットも事前に決めておくと内容にばらつきが生じることを防げるでしょう。
記録は法的証拠にもなります。そのため丁寧に扱う必要があることも、組織全体で理解しておくことが大切です。
事故の原因調査・対策
事故が発生した原因を分析し、明確にすることは事故の再発防止に欠かせません。
職員側の要因なのか、利用者や環境的な要因なのか、複合的に関連し事故が発生したのかなど、多角的な観点から多職種のチームで検討を行うことが大切です。
分析結果に基づいて具体的な再発防止策を策定し、職員全体で共有・実施しましょう。また、対策も定期的に見直し、必要に応じて内容を更新することが重要です。
介護事故予防のPDCAサイクルを組織全体で継続することで、同様の事故が再発することを防ぎ、より安全で質の高い介護サービスの提供につなげることができます。
介護事故を防ぐには組織全体での対応が重要
介護事故の防止は、個々の職員の努力だけでは限界があり、組織全体での体系的な取り組みが不可欠です。
組織全体として事故防止に取り組む体制を構築し、継続的な改善を行うことが重要です。そのためには、経営層のリーダーシップが欠かせません。
事故防止を施設運営の最優先課題として位置づけ、必要な人員配置や予算確保を行うとともに、職員が安心して報告できる風土づくりに取り組むことが求められます。
また、事故防止に関する基本指針やマニュアルを策定し、全職員に周知徹底することも重要です。
安全管理委員会の設置も重要な取り組みの一つといえます。
他には、職員一人ひとりの知識と技術の向上を継続して行っていくことも、安全性を高めるためには重要なポイントです。
職員教育と研修の実施
職員一人ひとりの知識と技術の向上も、事故防止のために欠かせないものとなります。
新人職員:基本的な介護技術とともに、事故防止の重要性や具体的な予防方法について体系的な研修を実施
経験者:定期的な研修により最新の知識や技術の習得を支援し、慣れによる油断を防ぐ
といったように、対象者に合わせた内容の研修を行うことが大切です。
また、事業所内で発生した事故事例を教材として活用することで、より身近で具体的な学習が可能となるでしょう。
介護施設には、安全対策担当者の配置が義務付けられており、その役割を果たす上での職員教育は欠かせません。
安全対策担当者の役割と、組織的な安全対策の推進については、以下の記事を参考にしてみてください。
介護事故の防止に役立つICTツール
介護現場での事故防止に役立つさまざまなICTツールが開発されています。
こうしたICTツールを活用することで、職員の負担を軽減しながら、利用者の安全をより確実に守ることができます。
例えば、以下のようなICTツールがあります。
・見守りセンサー
・バイタルデータ自動記録システム
・介護記録ソフト
・インカム
・服薬管理システム
具体的なICTツールの導入事例や活用方法については、こちらの記事もご覧ください。
介護職員の最適な人員配置も重要なポイント
介護事故の防止において、職員の最適な人員配置は極めて重要な要素です。
職員のスキルや経験を考慮し、新人職員には経験豊富な職員をペアで配置するなど、バランスの取れたシフトを作成することが重要です。
しかし、シフト作成を担当する介護リーダーや管理者の多くは現場業務も行いながらシフトも作成するため、大きな負担がかかっている…といった介護現場が多いのではないでしょうか。
中には毎月数十時間かけて、シフトを作成している施設も少なくありません。
また作成したシフトに関しても、職員から、
「私の夜勤回数だけ多い」
「今月もきついシフトになっているのはなぜか」
「希望休が通らないと困る」
など不満が出ることもあり、シフト作成が担当者の精神的な負担になっているケースもあります。
こうしたシフト管理者の精神的な負担、時間的な負担を軽減し、効率的なシフト作成を実現するためには、介護業界に特化したシフト管理システムを利用する方法がおすすめです。
シフト管理システム「シンクロシフト」は、介護現場の複雑なシフト作成を効率化し、人員配置の最適化をサポートします。
これにより、職員の負担を軽減し、利用者へのきめ細やかなケア体制を維持することが可能になります。詳細はこちらをご覧ください。
まとめ
介護事故の防止は、介護現場で働く全ての職員にとって最重要課題の一つです。
事故防止において重要なのは、「防ぐべき事故を確実に防止する」という現実的な視点です。
適切なリスクマネジメントとヒヤリハット事例の活用により、多くの事故を予防することができるでしょう。
重要なのは、介護事故防止を職員個人の注意だけに頼るのではなく、組織全体として事故防止に取り組む体制を構築し、継続的な職員教育と環境整備を行うことです。
また、万が一事故が発生した場合は、利用者の安全確保を最優先に、迅速かつ適切な対応を行うことが重要です。
こうした事故発生時の対応の流れについても、マニュアルを作成しておくといざという時に統一した対応を取ることが可能となります。
本記事で紹介した考え方や事例、具体的な対策を参考に、現場ごとの状況や課題に合わせて対応を進めてみてください。
この記事の執筆者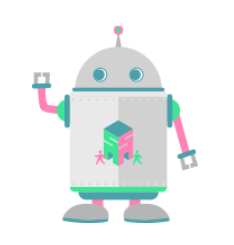 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
|---|
・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト
シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。
・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介
介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。
・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!
シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。
・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選
人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。





















